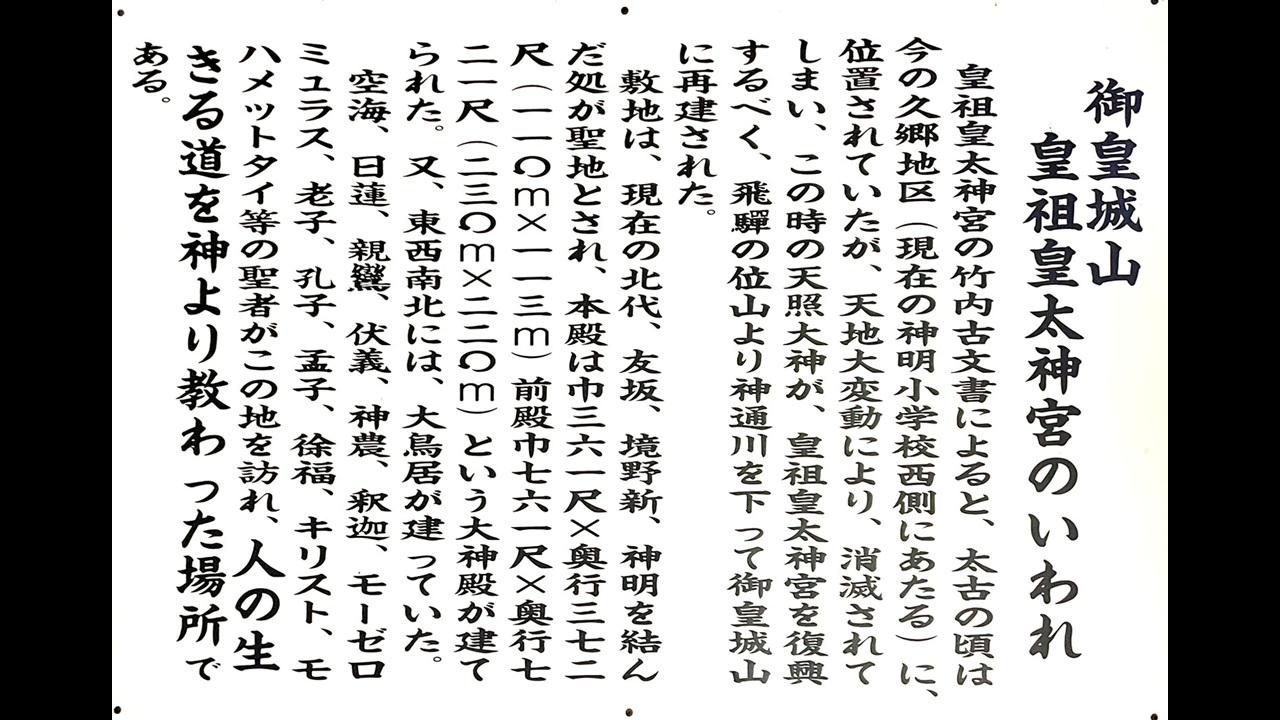<多用されている言葉>
・【宇宙剖判】……宇宙の天と地が開けること。宇宙の開闢。
・【天地剖判】……限身界(3次元)の出現
・【天職天津日嗣】……天から命じられた天皇の位。天職天皇として天津日嗣の御位。
「天職」……天から命ぜられた職。/「天津日嗣」……天皇の位。皇位継承。
「天津」……「天の」「天にある」の意。「日嗣」……天皇の位。
・【親祭】……天皇みずからが祭祀を行う
・【高御座】……①大極殿または紫宸殿の中央に設けられていた天皇の席。元旦・即位などの大儀のとき用いられた。現在は、京都御所紫宸殿に設けられ、即位礼のときにだけ用いる。三層の黒塗りの壇の上に八角形の屋形を据え、玉座をしつらえる。②天皇の位。皇位。
・【天神人祖一神宮】
「天日豊本葦牙気皇主身光大神天皇」「天日豊本葦牙気皇美神皇后宮」は、日の本皇統第一代として即位後、「天照日大神」以下、燿身界・駚身界諸神霊を地上に迎えて祀られた神宮。皇統第十代(上代第十代)「髙皇産神霊身光天津日嗣天皇」の時、「天神人祖一神宮」を「皇祖皇太神宮」と改称。
・【神宝】……天照日大神は、将来日の本の皇統継承の象徴たるべきものとして、天王の証としての宝―ひひいろがねの「は玉(宝球の玉)」―を天より降された。
・【十六菊紋】……十六方に光り輝くさまを現わした日輪章(菊型御紋章)。
・【個有日本】……日本だけに備わる。唯一の日本。
・【棟梁】……頭領
・【神幽る】……神去る。天皇・皇族など高貴な人が死ぬ。崩御する。
・【給う(=賜う)】……❶[動ワ五(ハ四)]《上位から下位に物や恩恵を与える意から、その動作主を敬う語となる。》①「与える」「くれる」の尊敬語。お与えになる。くださる。「おほめのお言葉を―・う」 ②人をおよこしになる。 ③自己側の動作に用い、尊大な語気を表す。目下の者に与える。くれてやる。 ④特に命令形は、上にくるはずの動詞を略して、命令・勧誘の意を表す。なさい。 ⑤(補助動詞)動詞・助動詞の連用形に付く。㋐その動作主が恩恵を与えてくださる意を表す。…てくださる。「神が恩恵を垂れ―・う」㋑その動作主を尊敬する意を表す。お…になる。お…なさる。「すぐれて時めき―・ふ」㋒尊敬の助動詞「す」「さす」に付いて「せ(させ)たまふ」の形で、程度の強い尊敬の意を表す。「たふとく問はせ―・ふ」㋓同輩以下の者に対し、親しみをこめたりやわらかに命令したりするのに用いる。「そんなにくよくよし―・うな」「早く行き―・え 」❷[動ハ下二]① 「もらう」の意の謙譲語。多く、飲食物の場合に
用いる。いただく。頂戴する。「魂は朝夕) に―・ふれど」 ②(補助動詞) ㋐主として動詞「聞く」「見る」に付いて、その動作を、恩恵を与えてくれる人(尊者)から受ける、いただくの意を表す。(尊者に)…させていただく。「我 聞き―・へき」㋑(かしこまりあらたまった会話・消息で用いる。平安中期以降の用法)自己または自己側の動作として用いる動詞(主として「思う」「見る」「聞く」)に付いて、聞き手に対してその動作をへりくだる意を表す。…させていただきます。…します。「かかる御事を見―・ふる(=拝見スル)につけて、命長きは心憂く思う―・へらるる(=存ゼラレマスル)世の末にも侍るかな」
・【~さるべからず】…… ~しなければならない。~せよ。
・【了】……おわる、さとる、しまう。
★――★――★
まえがき
・上梓(じょうし)……図書を版木にきざむこと。また、図書を出版すること。上木。出版。
・基教(ききょう)……キリスト教を略記した表現。
・渉猟(しょうりょう)……広くわたり歩いてさがし求めること。転じて、多くの書物などを読み漁ること。
・崇称(そうしょう)……「崇める」(尊いものとして扱う)から、尊いものとして称されているの意か。
・説話(せつわ)……はなし。ものがたり。特に、神話・伝説・童話などの総称。
・爾来(じらい)……それより後。その時以来。
・煙滅(えんめつ)……あとかたもなく消えてなくなること。
・手の舞い足の踏む所を知らぬ……喜びあまり、思わず知らず踊りだすのにいう。無我夢中で喜ぶさま。
・知悉(ちしつ)……知りつくすこと。詳しく知ること。
・翼賛(よくさん)……力をそえて(天子などを)たすけること。
・一諾(いちだく)……一たび承知すること。承知して引き受けること。
・印行(いんこう)……図書を印刷し発行すること。刊行。
・嚥下(えんげ)……のみくだすこと。
・真人(しんじん)……まことの道を体得した人。
・言挙げ(ことあげ)……言葉に出して特に言い立てること。とりたてて言うこと。揚言。
・奉行(ほうこう)……①上命を奉じて公事・行事を執行すること。また、その担当者。②武家の職名。(ぶぎょう)③宮中歌会始で、その事務を担当する人。
そえがき
・審神(さにわ)……古代の神道の祭祀において神託を受け、神意を解釈して伝える者。後には、祭祀の際に琴を弾く者を指すようにもなった。
・剖判(ほうはん、ぼうばん)……①天地などの開けわかれること。開闢(天地の開けはじめ、世界のはじめ)。 ②はっきりと区別がつくこと。
・謄写(とうしゃ)……①書きうつすこと。また、うつしとること。 ②謄写版で印刷すること。
・鳥の子(とりのこ)……「鳥の子紙」(鳥の子色の神の意で、中古から用いられた和紙の一種。平滑・緻密で光沢がある。)
・桐柾(きりまさ)……縦にまっすぐに通った木目(柾目)の桐。
・素雅(そが)……(身なり,部屋の飾りつけ,花の色合いなどが)さっぱりして気品がある,清楚で上品である。
・蹶起(けっき)……①勢いよく立ち上がること。②覚悟を決めて行動を起こすこと。
・譎詭(けっき)……①いつわりあざむくこと。②奇異なこと。変わっていること。
・運籌 (うんちゅう)……はかりごとをめぐらすこと。
・憤然(ふんぜん)……激しく怒る
・国体(こくたい)……国のありさま。国がら。国が最もたのみとする家来。(日本語での特別な意味で)国家の体面。
・通牒(つうちょう)……書面で通知すること。また、その書面。
・自若(じじゃく)……大事に直面しても落着きを失わず、平常と少しも変わらないさま。自如。
・布衍(ふえん)……①のべひろげること。ひきのばすこと。展開。 ②意義を広くおしひろげて説明すること。わかりやすく言い替えたり詳しく説明したりすること。
・密葬(みっそう)……ひそかに葬ること。内々で行う葬式。
・可惜(あたら)……惜しくも。もったいないことに。惜しむべき。あったら。
・国士(こくし)……①国中のすぐれた人物。 ②身をかえりみず、国家のことを心配して行動する人物。憂国の士。
・探察(たんさつ)……さがし、しらべること。探索。
・覆滅(ふくめつ)……完全に滅びること。また、くつがえしほろぼすこと。
・鏤骨(るこつ)……①骨に刻んで忘れないこと。②骨を刻むような苦労・苦心をすること。ろうこつ。
・創意(そうい)……新たに物事を考え出す心。新しい思い付き。独創的な考え。
・鍾(あつ)めて……①あつめる。かたまってあつまる。②中国周代の容積の単位。約四九・七リットル。③かね。つりがね。(同)鐘。④酒器。さかつぼ。さかずき。〔音〕ショウ
・巧遅(こうち)……巧みではあるが仕上げのおそいこと。
・拙速(せっそく)……仕上りはへたでも、やり方が早いこと。
・尚ぶ(たっとぶ、とうとぶ)……尊ぶ。貴ぶ。
・糾問(きゅうもん)……罪を問いただすこと。糾明。吟味。
・一朝有事(いっちょうゆうじ)……ひとたび事件が起こること。また一大事の際には助勢のために駆けつけること。
・鋳潰(いつぶ)し……金属の器物をとかして地金にかえす。
・寄寓(きぐう)……①他人の家に身を寄せること。②かりのすまい。
・張作霖(ちょうさくりん)……中国の軍人・政治家。奉天派軍閥の総帥。字は雨亭。遼寧海城の人。馬賊の出身。東三省を支配下に収め、1927年北京で大元帥。同年国民政府の北伐軍と戦って河南で大敗。28年奉天(今の瀋陽)に入ろうとして関東軍の陰謀による列車爆破で死亡。なお、当時の日本政府は爆殺事件の真相を秘匿するため、満州某重大事件と呼んだ。(1875〜1928)
・清居(せいご?)……清らかな住まい?
・糾合(きゅうごう)……一つによせあつめ、まとめること。
・好事魔多し(こうじまおおし)……よいこと、うまくいきそうなことには、とかく邪魔がはいりやすいものである。
・惹起(じゃっき)……事件・問題などをひきおこすこと。
・呉佩孚(ごはいふ)……中国の直隷派の軍閥。山東の人。1924年第2次奉直戦争に敗れ、26年春以来張作霖と提携、蒋介石の北伐に敗北、北京に隠棲。(1873〜1939)
・謀報(ちょうほう)……相手の様子をさぐって知らせること。また、その知らせ。
・後送(こうそう)……①後方へ送ること。特に戦場などで、前線から後方へ送ること。 ②あとから送ること。
・離奉帰綾……奉天を離れ、綾部に帰る
・由因(ゆかり)……①物事が起こった理由。わけ。いわれ。来歴。由緒 。②そうするための方法。
・軒軽(けいけん)……軽快で作りのよい車。
・玉綸(ぎょくりん)……玉+綸①絹糸をより合わせたひも。「綸綬」② 釣り糸。「垂綸」
③ おさめ整える。「経綸」④天子の言葉。「綸言・綸旨」
・有道(ゆうどう)……正しい道にかなっていること。徳をそなえていること。正道を行うこと。
・諸賢(しょけん)……①多くの賢人。②皆さん。あなたがた。
・浄机(じょうき)……きよらかな机。
・呈上(ていじょう)……人に物などをさしあげること。
神示現示の解
・神示
・文化(1804~1818)
・現示
・御宇(ぎょう)……天子の治め給う御世。
・黒住宗忠に天命直授(てんめいじきじゅ)……備前岡山藩の守護神社・今村宮の神官だった黒住宗忠(1780~1850)は、死を覚悟するほどの病を克服し、満34歳の誕生日だった冬至の日に、昇る朝日を拝む「日拝」の最中に天啓を得、天照大御神と一体になるという「天命直授」の宗教的体験をし、江戸時代(文化11年11月11日・1814年)に立教。幕末三大新宗教に数えられ、神道十三派の草分けである教派神道。教えは、一切万物すべての親神が天照大御神で、その尊いはたらきの中であらゆるものが存在し、人は天照大御神の「分心」をいただいた神の子であるという世界観。*神霊正典では、「天照大御神」は「天照日大神」。
・神啓
・垂示(すいじ)……①教えを説くこと。②禅宗で、師家しけが大衆だいしゅに要義を説くこと。示衆。
・個有日の本……「固」は「もとより」の意なので、「固有」(天然に有すること。もとからあること。その物だけにあること)。「個」は「ひとつの」「個に具わり、他とはちがう」の意なので、「個有日の本」「日の本個有」は「日本ただ一つだけに備わる」の意味ととれる。
・湮滅(いんめつ)……堙滅。あとかたなく消えてなくなること。すっかり隠しなくすこと。
・慮る(おもんばかる)……よくよく考える。考えはかる。思いめぐらす。
・隠匿(いんとく)……①包み隠すこと。秘密にすること。かくまうこと。②隠れた悪事。心中に蔵する罪悪。隠悪。
・歪曲(わいきょく)……事柄を意図的にゆがめ曲げること。
・真箇(しんこ)……まこと。全く。
・純正(じゅんせい)……①純粋で正しいこと。純粋でまじりけのないこと。 ②それ自体の価値や理論を主として、応用や実利を主としないこと。
・符合(ふごう)……①割符が双方合うこと。 ②二つ以上の事物がぴったりと合うこと。合致すること。
・毫釐(ごうり)……きわめて少ない分量。⇒ 毫釐の差は千里の謬
・説述(せつじゅつ)……意見や考えを説き述べること。
第1章 宇宙とその動き
・・・・・ 3
・環(たまき)……①玉の輪。②輪の形をなすもの。
・楷梯……「楷」は「①書体の一つ。楷書。②ウルシ科の落葉高木。」なので、「階梯」が正しいと思われる。「階梯(かいてい)」……①学問・芸術などの手ほどき。また、それを説いた書物。入門書。②学問・芸術などを学ぶ段階。また、物事の発展の過程。③器械体操で斜めにかけて使うはしご。また、それを使ってする体操。
・太初(たいしょ)……天地のひらけたはじめ。太始。
・縁(えん)……①へり。ふち。②家の外側に添えた細長い板敷。③原因をたすけて結果を生じさせる作用。直接的原因(因)に対して間接的条件。また、因と同義にも用いる。④ゆかり。つづきあい。関係。⑤人と人とのつづきあい。婚姻の関係。
・薄靡(たなび)きて……(雲・霞または煙が)薄く横に長く引く。
・淹滞(つつ)きて……「淹滞(えんたい)」は、①久しくとどまること。②才能ある人物がいつまでも下位にとどまっていること。
・蕃殖(はんしょく)=繁殖……(植物が)しげり増えること。(動物が)増えはびこること。生殖により個体数を増すこと。
・せられざるべからず……「ざるべからず」とは、(二重否定で意味を強めて)…しなければならない。…せよ。
・繁茂(はんも)……草木の生いしげること。
・思惟(しい)……心に深く考え思うこと。
・謂(いわれ)……(由来として)言われていること。来歴。理由。
・自在神(じざいしん)……世界創造をなしとげる主宰神
・律する(りっする)……おきてを定める。また、一定の規準によって処置する。
・流転(るてん)……①流れ移ること。移り変わること。②〔仏〕生まれかわり死にかわりして、きわまりないこと。
・先見(せんけん)……事があらわれる前に見ぬくこと。さきを見通すこと。
・統量(むねりょう)……?
・全一(ぜんいつ)……完全に一つにまとまっていること。統一していること。
・ざるべからず……[連語]《打消しの助動詞「ざり」の連体形+連語「べからず」》(二重否定で意味を強めて)…しなければならない。…せよ。
・べからざる……議論する余地がない。否定することができない。明らかな。
・常恒(じょうごう)……物事がいつまでも変わらないこと。また、そのさま。
・知食(しろしめ)す……①お知りになる。ご存知である。②領せられる。お治めになる。③お世話なさる。
・領(りょう)する……①領地として所有する。②受け取る。また、承知する。了承する。③魔物などがとりつく。
・没却(ぼっきゃく)……なくすること。無視すること。
・因襲(いんしゅう)……①昔からのしきたりや習わしにしたがうこと。②(→)因習に同じ。
・退嬰(たいえい)……あとへ退くこと。しりごみすること。新しい事を、進んでする意気ごみのないこと。
・生々(せいせい)……生いたち育つさま。また、いきいきしているさま。「生生(なまなま)」は、①いかにも生なまであるさま、②いいかげんなさま。未熟なさま。中途半端。
・継統(けいとう)……①系統をうけつぐこと。②皇位を継承すること。
・自在(じざい)……①束縛も支障もなく、心のままであること。思いのまま。②自在鉤かぎの略。③〔仏〕仏・菩薩が望むとおりに物事をなしうること。この力を自在力といい,仏・菩薩を自在人という。
・修理固成(おさめつくりかためなせ)……古事記「修(おさ)め理(つく)り固(かた)め成(な)せ」。
古事記の国生みの場面で、多くの神々がイザナギ、イザナミの二柱の神に「このただよえる国を修め理り固め成せ」と命じたと。
・裡(り)……物の内側。ある状態のうち。「盛会―に終わる」)
・踵(きびす)を接する……人のあとに密着して行く。転じて、いくつかの物事が引き続いて起こる。
・爾後(じご)…‥この後。その後。それ以来。
・悠久(ゆうきゅう)……長く久しいこと。果てしなく長く続くこと。永久。
・天津(あまつ)……「天の」「天にある」の意。「―日」「―神」。ツは上代の助詞。
・神則(かみのり?)……神の規範、規則?
・自恣(じし)……① 自分の欲するままに行動すること。きままなさま。
・解放(かいほう)……解き放つこと。束縛を解いて自由にすること。
・放縦(ほうじゅう)……気ままなこと。わがまま。
・而して(しかして)……そうして。そうであるから。
・暫時(ざんじ)……少しの間。しばらく。しばし。
・熄(や)む……火が消えるように滅びてなくなる。消えてなくなること。やむこと。また、やめること。
・玲瓏(れいろう)……①玉などが透き通るように美しいさま。また、玉のように輝くさま。② 玉などの触れ合って美しく鳴るさま。
・己まず(やまず)……「已むない」「已むに已まれぬ」「已むを得ず」
・思索(しさく)……物事のすじみちを立てて深く考え進むこと。考えめぐらすこと。
・消息(しょうそく)……①動静。安否。様子。事情。 ②訪れること。往来。また、来意を告げること。案内。 ③文通すること。また、その手紙。
第2章 宇宙 解判
・・・・・ 10
・活現(かつげん)……事実をいきいきと目に見えるようにあらわすこと。
・相(そう)……①すがた。ありさま。外見。形状。 ②物にあらわれた吉凶。また、それを見ること。③〔仏〕性質。特徴。現象的なすがた。
・凝る(こる)……①散り散りにある同質のものが一つに寄り固まる。ひと所に集まり寄る。凝結する。②冷えて固まる。凍る。
・生々(せいせい、生生)……生いたち育つさま。また、いきいきしているさま。
・義(ぎ)……①道理。条理。物事の理にかなったこと。人間の行うべきすじみち。 ②利害をすてて条理にしたがい、人道・公共のためにつくすこと。 ③意味。わけ。言葉の内容。
・燿く(かがやく)……①まぶしいほど光る。きらきら照りきらめく。②顔を赤くして恥かしがる。③立派で、はなばなしく見える。明るく生き生きとして見える。
・妙果(みょうか)……すばらしい結果。仏果のこと。仏の悟り。
・稜威(りょうい)……天子・天皇の威光。御厳(みいつ)。
・六合(りくごう)……天地と四方。宇宙全体。
・駛り(はせり?)……①はせる。ウマをはやく走らせる。 ②はやい。にわか。
・神通(じんつう、じんずう)……超人的能力。通力。通。
・自往(じおう)……「往」は「①人・動物・乗り物が,移動する。②動作者が話し手とともに移動する。」なので、「自ら移動する」の意か?
・寿(ことぶき)……①めでたいこと。②めでたいことを祝うこと。また,祝いの言葉や儀式。ことほぎ。③いのち。また,いのちの長いこと。長命。長寿。
・司配(しはい)……? 辞書にはないが、浅野和三郎(小桜姫物語)「いかなる教えを信じても産土の神の司配を受けることに変わりはないが」「少櫻姫と名乗る他の人格が彼女の体躯を司配して、任意に口を動かし」、与謝野晶子(鏡心灯語抄)「実際に全夫人をその貞操倫理の金科玉条で司配することは出来なかった」と使われている。
・威大(いだい)……「威」は「人をおそれ従わせる勢い・力・品格。」
・狭小(きょうしょう)……狭く小さいこと。
・旋転(せんてん)……くるくると回ること。回転すること。また、くるくると回すこと。
第3章 地球修理固成
・・・・・ 15
・一塊(ひとかたまり、いっかい)……一つのかたまり。一つにかたまっていること。また、そのかたまり。
・建分(けんぶん?)……建てたり分けたりの意味か?
第4章 神界統
・・・・・ 17
・主班(しゅはん)……第一の席次。最高の席次。首席。特に、内閣の首席の人。内閣総理大臣。
・現出(げんしゅつ)……あらわれ出ること。あらわし出すこと。出現。
第5章 人類創造
・・・・・ 20
・造化(ぞうか)……①天地の万物を創造し、化育すること。また、造物主。②造り出された天地。宇宙。自然。また、自然の順行。③ものをつくり出すこと。造作。
・降下(こうか)……①高い所からおりること。さがること。②高い地位の人から命令などがくだされること。
・躬(きゅう)……① み。からだ。② みずから。自分で。
・親ら(みずから)……天子が直接行うときに用いる。
・鋭意(えいい)……心をはげましつとめること。一生懸命励むこと。専心。
・踏襲(とうしゅう)……先人のやり方や説をそのまま受け継ぐこと。前人のあとをそのまま受けつぐこと。
・蘊醸(うんじょう)……「蘊(うん)」①つみたくわえる。たくわえ。②おくそこ。奥深い。――から、「蘊醸」は、「たくわえ醸(かも)す」の意か?
・附与(ふよ)……授け与えること・
・育成(いくせい)……やしないそだてること。立派に育て上げること。
・化成(かせい)……①育ててその生長を遂げさせること。 ②形を変えて他の物になること。 ③徳化されて善にうつること。 ④化学的に合成すること。
・如上(じょじょう)……上に述べたところ。上述。
・蜒延(えんえん)……「蜿蜿」は、ヘビや竜がうねうねと動くさま。「蜿蜿」は「蜒蜒」「延延」とも書くことから、「蜿延」はその合わさった語と思われる。一般に「蜿蜿長蛇の列」と用いる。
・冱寒(ごかん)……凍って寒さのきびしいこと。
・交々(こもごも)……それぞれ。
・資料(しりょう)……①もとになる材料。特に、研究・判断などの基礎とする材料。②試行2の結果。または結果を数量で表したもの。
・俟つ(まつ)……①来るはずの人や物事を迎えようとして時をすごす。②用意して迎える。もてなしをする。③のけておいて、後の用に供する。④(多く「俟つ」と書く)頼りとする。期待する。よる。
・御親(おんみずか)ら
第6章 人類界の統一[日本皇室の発祥]
・・・・・ 23
・天職天津日嗣(てんしょくあまつひつぎ)……天から命じられた天皇の位。
・天職(てんしょく)……①天から命ぜられた職。 ㋐天子が国家を統治する職務。 ㋑神聖な職務。 ㋒その人の天性に最も合った職業。②遊女の階級の一つ。天神の別称。
・天津(あまつ)……「天の」「天にある」の意。
・日嗣(ひつぎ)……天皇の位。皇位。天位。あまつひつぎ。
・天津日嗣(あまつひつぎ)……天皇の位。皇位。天位。あまつひつぎ。
・神勅(しんちょく)……①神のおつげ。 ②天照大神が皇孫瓊瓊杵尊をわが国土に降す時に、八咫鏡とともに授けたということば。
・日刺方(?)
・真柱(しんばしら)……①(→)「しんのはしら」に同じ。②中心となる人物。③(「真柱」と書く)天理教で首長の称。
・高御座(たかみくら)……①天皇の位の称。天位。②天皇の玉座。
・皇祖……「人類界統治の始祖」
・天璽(てんじ)……天つ神の子孫としての証拠の品。皇位のしるし。あまつしるし。
・儼(げん)として……厳しく
・確乎(かっこ)……たしかなさま。信念などがしっかりして動かないさま。
・儼乎(げんこ)……おごそかでいかめしいさま。きっぱりとして威厳を保つさま。
・万世一系(ばんせいいっけい)……天子の血統が永遠にわたって、かわらず続くこと。
第7章 神代の神政政治
・・・・・ 25
・起伏(きふく)……①高くなったり低くなったりしていること。②盛んになったり衰えたり、さまざまな変化があること。
・生起(せいき)……ある事件や現象などが現れ起こること。
・齟齬(そご)……物事がうまくかみ合わないこと。食い違うこと。ゆきちがい。
・酷似(こくじ)……非常によく似ていること。そっくりなこと。
・常(つね)……①いつでも変わることなく同じであること。永久不変であること。②いつもそうであること。ふだん。平素。③特別でないこと。普通。平凡。④昔からそのようになるとされていること。当然の道理。ならい。ならわし。⑤他の例と同じように、その傾向のあること。とかくそうありがちなこと。
第8章 事実の国
・・・・・ 27
・国體(こくたい)……①国家の状態。くにがら。②国のあり方。国家の根本体制。③主権の所在によって区別される国家の形態。君主制・共和制など。④「国民体育大会」の略。
・不拘(かかわらず)……① 後文に述べられる結果が、前文に述べられた障害となるべき条件から順当に予想されるものと反対であることを表わす。② 後文に述べられる事柄が、前文の条件のいかんに関係なく、常に成立することを表わす。
・大凡(おおよそ)……①すべて数えて。おしなべて。②大体において。ほぼ。およそ。③なみひと通りであるさま。世間一般。なみたいてい。
・先君後民論(せんくんこうみんろん)……統治者(君主)を先に考え、民衆を後に考えること。政治において「先ず統治者(君主)の利益を優先し、その後に民衆の利益を考える」という考え方を指します。これは、徳治主義や支配者が民衆に幸福をもたらすという伝統的な考え方と対照的に、より支配者の利益を重視する立場を表明します。
・尊崇(そんすう)……とうとびあがめること。
・不用(ふよう)……①いらないこと。用のないこと。②役に立たないこと。無駄なこと。駄目。無益。③しないでよいこと。無用なこと。④人に迷惑のかかる乱暴をはたらくこと。不届きなこと。⑤怠けがちなこと。無精。
・惟神(かむながら、かんながら)……①神でおありになるまま。神として。②神の御心のままで人為を加えないさま。神慮のまま。
・附会(ふかい)……無理につなぎ合わせること。こじつけること。
・幽玄(ゆうげん)…… ①奥深く微妙で、容易にはかり知ることのできないこと。また、あじわいの深いこと。情趣に富むこと。②上品でやさしいこと。優雅なこと。③日本文学論・歌論の理念の一つ。優艶を基調として、言外に深い情趣・余情あること。その表現を通して見られる気分・情調的内容。
・放擲(ほうてき)……ほうり出すこと。なげうつこと。なげすてること。うちすてること。
・をだに……せめて~だけでも。せめて~なりとも。
・淵源(えんげん)……物事のよってきたるもと。みなもと。根源。
・至厳(しげん)……きわめてきびしいこと。非常におごそかなさま。
・確然(かくぜん)……物事がたしかで、しっかりと定まっているさま。
・至幸(しこう)……この上もない幸福。
・至楽(しらく)……この上もなく楽しいこと。きわめて楽しいこと。また、そのさま。
・べからず(可からず)……①…してはいけない。…すべきではない。②…することができない。
第9章 天の岩戸閉め[神人の乖離混乱進展時代]
・・・・・ 29
・乖離(かいり)……そむき離れること。はなればなれになること。
・充足(じゅうそく)……十分に満たすこと。満ちたりること。
・常規(じょうき)……①通常の規則。常例。 ②標準。
・顕現(けんげん)……はっきりと現れること。明らかにあらわし示すこと。
・自家撞着(じかどうちゃく)……②前後が一致しないこと。つじつまが合わないこと。矛盾。
・惹帰(じゃっき?)……惹き起して帰って来る
・反逆(はんぎゃく)……国家や権威にそむくこと。むほん。
・紊乱(びんらん)……乱れること、乱すこと。
・杜絶(とぜつ)……ふさがり絶えること。とだえること。
・體して(たいして)……「体する」命令や教えなどを心にとどめて守るようにする。
・黙過(もっか)……知らぬ風をして、そのままにしておくこと。みのがし。
第10章 神政政治の動揺
・・・・・ 32
・橦(ツキ)……「撞之大神[月の大神]。橦は、雲南地方に産する木の名。
・珍(うず)……(神や天皇に関して用いる)貴く立派であること。尊厳なこと。
・詰らせ(なじらせ)……相手の過失や不満な点などを問いつめる。問いつめて責める。詰問する。
・引き落とす(ひきおとす)……①前や下に引いて落とす。②差し引く。②公共料金などを、支払人の預金口座から受取人の口座へ所定期日に送金する。
・一に(いつに)……①ひとつには。別に。或いは。また。②専ら。ひとえに。全く。
・策動(さくどう)……ひそかに策を講じて事を進めること。謀略をめぐらすこと。いわゆる悪巧みを指すことが多い。
・掌中(しょうちゅう)……①てのひらの中。②自分のものとして自由にできる範囲内。また、その中にあること。手中。
・爪牙(そうが)……①つめときば。②主人の手足となって働く家臣。爪牙耳目。
・葛藤(かっとう)……もつれる
・嚆失(こうし)……①かぶら矢。②物事のはじまり。最初。
第11章 善悪の発生[神の戯曲]
・・・・・ 34
・機縁(きえん)……① 仏語。教えを求める資質が、教えを説くきっかけとなること。② ある物事が起こったり、ある状態になったりする、きっかけ。縁。
・英明(えいめい)……才知がすぐれて事理に明るいこと。すぐれて賢いこと。
・謂(いわれ)……①物事が起こったわけ。理由。②由緒。来歴。
・闡明(せんめい)……はっきりしていなかった道理や意義を明らかにすること。闡(あきらか)
・一斑(いっぱん)……全体からみてわずかな部分。一部分。
・覗う(うかがう)……①見つからないように物陰などから様子を見ること。②様子見ながら機会を待つこと。③相手の反応に気を配りながら様子を見ること。……覗き見る
・分明(ぶんめい)……①他との区別がはっきりしていること。あきらかなこと。また、そのさま。②明らかになること。
・依る(よる)……①それを原因とする。起因する。②物事の性質や内容などに関係する。応じる。従う。③動作の主体をだれと指し示す。④それと限る。⑤手段とする。⑥頼る。依存する。
・所以(ゆえん)……わけ。いわれ。理由。
・窺い知る(うかがいしる)……すでにわかっていることをもとにして推測し、そのあらましを知る。だいたいの見当をつける。
・訓せし(よみせし)……訓み=読み
第12章 第1次神政内閣 (大地将軍 常世姫大神)
・・・・・ 37
・首班(しゅはん)……第1の席次。特に、内閣で総理大臣。
・性来(せいらい)……本来の性質。うまれつき。
・因縁(いんねん)……①〝[仏]ものごとの生ずる原因。因は直接的原因、縁は間接的条件。また、因と縁から結果(果)が生ずること。縁起。転じて、定められた運命。②きっかけ。動機。しかるべき理由。③由来。来歴。④ゆかり。関係。縁。
・大同小異(だいどうしょうい)……大体は同様であるが、小部分だけが異なっていること。大変似ていること。似たりよったり。
・終熄(しゅうそく)……事がおわって、おさまること。終止。
・氷解(ひょうかい)……氷がとけるように,疑いやうらみの気持ちなどがなくなること。
・炬火(きょか)……たいまつ。かがり火。
・困却(こんきゃく)……困りきること。
・攝津国(せっつこく)……①旧国名の一。大阪府西部と兵庫県南東部に相当。五畿内の一。摂州。津国(ツノクニ)。②大阪府中北部,大阪市の北東に隣接する市。
・殿陣(しんがり)……軍隊が退却するとき,最後尾にあって,追ってくる敵を防ぐ役。
・陣没(じんぼつ)……戦地で死ぬこと。出征中に死亡すること。陣亡。
・魔痺(まひ)……「麻痺」(一般的には、四肢などが完全に機能を喪失していることや、感覚が鈍って、もしくは完全に失われた状態を指す。)
・斃(たおれる)……たおれる。たおれて死ぬ。ほろびる。
・是認(ぜにん)……人の行為や思想などを、よいと認めること。
・相当(そうとう)……①価値や働きなどが、その物事とほぼ等しいこと。それに対応すること。②程度がその物事にふさわしいこと。また、そのさま。③かなりの程度であること。また、そのさま。
・反逆(はんぎゃく)……権威・権力などにさからうこと。
第13章 皇統第1代[上代第1代]天日豊本葺牙気皇主身光大神天皇
・・・・・ 42
・天璽(てんじ)・・・・・・天皇のしるしとして、歴代に伝える重宝。あまつしるし。
・光芒(こうぼう)……光のほさき。すじのように見える光。
・神明(カミアカリ、しんめい)……①神。神祇。②神のように明らかな徳。 ③祭神としての天照大神の特称。 ④人の心。精神。
・勧請(かんじょう)……①神仏の来臨や神託を祈り願うこと。また、高僧などを懇請して迎えること。②神仏の分身・分霊を他の地に移して祭ること。
・濫觴(らんしょう)……ものごとのはじまり。物の始まり。物事の起原。おこり。もと。
・島嶼(とうしょ)……しま。島々。嶼」は小さな島)
・神幽(かみさ)り……(神去り) … 天皇など、高貴の人が死去する。崩御(ほうぎょ)する。薨去(こうきょ)する。かんさる。かむさる。「幽(かそけ)し」は、かすかだ。ほのかだの意味。程度・状況を表す語で、美的なものについて用いる。
第14章 第2次神政内閣(地上九大神 (地上姫大神)
・・・・・ 50
・局(きょく)……①役所などの事務の一区分。また、その一区分をつかさどる所。②物事が終了すること。③当面の情勢。事態。
・極(きょく)……物事の最上・最終のところ。きわみ。はて。
第15章 皇統第2代[上代第2代]造化気満男身光神天皇
・・・・・ 51
・越中立山……立山連峰は、富山県と岐阜県に連なる飛騨山脈の一部で、一番高い山が、立山。
第16章 第3次神政内閣(佐田彦王大神 佐田子姫大神)
・・・・・ 52
・出御(しゅつぎょ)……天皇・三后がおでましになること。
・股肱(ここう)……手足となって働く、君主が最もたよりとする家臣。
・放逐(ほうちく)……おいやること。おいはらうこと。追放。
・憤懣(ふんまん)……怒りが発散できずいらいらすること。腹が立ってどうにもがまんできない気持ち。
・囲統?(?)……囲まれて、統括する? 統(すべる)は「全体をまとめて支配する。統轄(多くの人や機関を一つにまとめて管轄する)する。」の意。
・放埓(ほうらつ)……①勝手気ままでしまりのないこと。また、そのさま。②身持ちの悪いこと。酒色にふけること。また、そのさま。
・姦悪(かんあく)……心がねじけていて悪いこと。また、そういう人や、そのさま。
・一時に(いちどきに)……いちじに。一度に。いっしょに。
・竄入(ざんにゅう)…… ①にげこむこと。 ②誤って入りまじること。まぎれこむこと。
・閉塞(へいそく)……閉じふさぐこと。
・素志(そし)……平素の志。かねての願い。
・貫徹(かんてつ)……貫きとおすこと。貫きとおること。
・蠢動(しゅんどう)……①虫などのうごめくこと ②転じて、取るに足りないものが策動すること。
・爪牙(そうが、そうげ)……①(動物が武器とする)つめときば。転じて、人を攻撃し傷つけるもの。②主君の身を守る臣。手足となって働く者。
・防遏(ぼうあつ)……ふせぎとめること。
・招致(しょうち)……招き寄せること。
・与る(あずかる)……①関係する。かかわる。②分け前をいただく。③目上の人から、受ける。こうむる。
・閉塞(へいそく)……とじふさぐこと。とざされふさがること。
第17章 皇統第3代[上代第3代]天日豊本黄人皇主身光神天皇
・・・・・ 57
・大幣(おおぬさ)……①大きな串につけたぬさ。祓えに用いる。大麻。②(上記の歌から)引く手あまたであること。引っぱりだこ。
・天津日嗣(あまつひつぎ)……天つ神の位、系統を受け継ぐこと。皇位を継承すること。また、皇位。
・天壌(てんじょう)…… あめつち。天地。
・窮る(きわま)る……①ぎりぎりの状態までいく。限度・限界に達する。②
・真個(しんこ)……まこと。全く。
・例(れい)……①過去または現在の事物で、典拠・標準とするに足るもの。②慣習とすること。しきたり。③規則。規定。 ④一般的、または日常的であること。普通。⑤同種類の多くの事項を類推させるために、特にその中から指摘する事項。たとえ。
第18章 第4次神政内閣(八尾大陣大神 大鶴姫大神)
・・・・・ 63
・攪乱(かくらん)……かき乱すこと。
・聴許(ちょうきょ)……訴えや願いをききいれて許すこと。
・体(たい)する……命令や教えなどを心にとどめて守るようにする。
・如(し)かず……①及ばない。かなわない。②…に越したことはない。…が最もよい。
・放擲(ほうてき)……投げ出すこと。捨ててかえりみないこと。
・一決(いっけつ)……①議事・相談などが一つに決まること。また、決めること。②固く決心すること。
・由(よし)……①)物事が起こった理由。わけ。また、いわれ。来歴。由緒。②そうするための方法。手段。手だて。また、かこつける方法。口実。③物事の内容。事の趣旨。むね。④伝え聞いた事情。間接的に聞き知ったこと。⑤それらしく見せかけること。体裁をつくること。また、表面にあらわれたようす。体裁。格好。⑥風情。趣。また、教養。
・軒昻(けんこう)……意気が高く上がるさま。気持ちが奮い立つさま。
・諮(はか)る……他人に意見を求めたり、相談したりすること。
・建議(けんぎ)……①意見を申し立てること。また、その意見。②明治憲法下で、両議院が政府に対して意見や希望を申し述べること。
・固陋(ころう)……古い習慣や考えに固執して、新しいものを好まないこと。また、そのさま。
・建言(けんげん)……政府・上役などに対して意見を申し立てること。また、その意見。
・狂喜(きょうき)……異常なまでに喜ぶこと。
・手の舞い(てのまい)……「手の舞い足の踏むところを知らず」=非常に喜んでいるようすのたとえ。転じて、非常に動転しているようすのたとえ。
・隠然(いんぜん)……表面ではわからないが、陰で強い力を持っているさま。
・黙過(もっか)……知っていながら黙って見すごすこと。
第19章 皇統第4代[上代第4代]天之御中主神身光天皇
・・・・・ 68
・草賊(そうぞく)…… ①山野にうろついて旅人などを襲う盗賊。おいはぎ。こぬすびと。 ②取るに足りない賊徒。③ 反乱、一揆など、支配者に歯向かう賊徒。また、それらをののしっていう語。
・蜂起(ほうき)……蜂が巣から一時に飛びたつように、大勢の人々が一斉に立ち上がって実力行使の挙にでること。
・撃破(げきは)……①敵をうちやぶること。②敵に損害を与えること。
・跋扈(ばっこ)……上を無視して権勢を自由にすること。転じて一般に、勝手気ままにふるまうこと。のさばりはびこること。
・嚆矢(こうし)…… ①かぶらや。鳴り響く矢。 ②物事の最初。はじまり。起り。起源。
・唵(おん)……《(梵)oṃの音写》インドの宗教や哲学で、神聖で神秘的な意味をもつとされる語。仏教でも、真言や陀羅尼(だらに)の冠頭に置かれることが多い。帰命(みみょう)・供養あるいは仏の三身を表すとするなど、種々の解釈がある。
・蕃殖(はんしょく)……(植物が)しげり増えること。(動物が)増えはびこること。生殖により個体数を増すこと。
・卑近(ひきん)……てぢかでたやすいこと。ありふれたこと。高尚でないこと。
・片影(へんえい)……わずかのかげ。わずかに見える物の姿。また、ある側面。
・該(がい)……問題になっている事物を指していう語。その。この。
・人文(じんぶん)……①人の世に行われる節道。人倫の秩序。②人類の文化。 ③人文科学の略。
第20章 第五次神政内閣(大野大陣大神 大野姫大神)
・・・・・ 73
・陸続(りくぞく)……ひっきりなしに続くさま。
・乱麻苅菰……天下麻の如く乱れる。(乱麻は、乱れもつれた麻・糸。苅菰は、刈り取った真菰、それで織ったむしろ。)
・扶植……うえつける。
・経営(けいえい)……①力を尽くして物事を営むこと。工夫を凝らして建物などを造ること。 ②あれこれと世話や準備をすること。忙しく奔走すること。③継続的・計画的に事業を遂行すること。特に、会社・商業など経済的活動を運営すること。また、そのための組織。
・蹯居……蟠居? (根を張って動かないこと、根拠地を占めて勢力をふるうこと)
第21章 皇統第5代[上代第5代]天八下王身光天皇
・・・・・ 74
第22章 皇統第6代[上代第6代]天目降美身光天皇
・・・・・ 75
・着御(ちゃくぎょ)……天皇や貴人を敬って、その到着・着座をいう語。
・還御(かんぎょ)……皇・法皇・三后が出かけた先から帰ること。転じて、将軍・公卿が出先から帰ることにいう場合もある。還幸。
・仰出(おおせだ)す……仰せになる。命令を発せられる。
第23章 皇統第7代[上代第7代]天相合美身光天皇
・・・・・ 76
・同列(どうれつ)……①列が同じであること。同じ列。②地位・程度・資格・待遇などが同じであること。
・世幸男(よさちを)……女帝の配偶者で、必ず皇胤(男帝の男系子孫)。
第24章 皇統第8代[上代第8代]天八百足身光天津日嗣天皇
・・・・・ 77
第25章 皇統第9代[上代第9代]天八十万魂身光天津日嗣天皇
・・・・・ 77
・鑿(さく)……「鑿井」は 「井戸を掘ること」から、「井戸鑿」は、井戸を掘ることと思われる。
・臼杵(うすきね)……臼と杵
第26章 世界文化の発祥
・・・・・ 78
・案出(あんしゅつ)……かんがえ出すこと。
・大御心(おおみこころ)……天皇の心。
・扶植(ふしょく)…… ①うえつけること。 ②たすけたてること。扶持すること。
・際(さい)する……でくわす。ある場面にあう。
・磐城国(いわきのくに)……戊辰戦争終結後の1869年(明治2年)につくられた地方区分のひとつ。(現在の福島県浜通りなど)
第27章 第6次神政内閣(道成義則大神 気津久姫大神)
・・・・・ 80
・激甚(げきじん)……きわめてはげしいこと、はなはだしいこと。また、そのさま。
・堵(と)に安(やす)んじて……①垣根で囲まれた住居の中で安心している。安心して生活する。 ②安心する。安堵する。
・謳歌(おうか)…… 声をそろえてほめたたえること。
・忍(しの)びない……我慢できないこと。
・奢侈(しゃし)……必要程度や分限を超えたくらしをすること。おごり。ぜいたく
・事(こと)とする…… 仕事とする。もっぱら…する。
・暴戻(ぼうれい)…… あらあらしく道理にもとること。
・事(こと)を構(かま)える……好んで事件を起こそうという態度をとる。物事を荒立てようとする。
・誣罔(ふもう)……いつわること
・罪過(ざいか)……罪と過ち。法律または道徳に背いた行為。
・縷々(るる)……①細く絶えずに続くさま。②こまごまと述べるさま。
・瀆罪(とくざい?)……「贖罪」のあやまりか? 「贖罪」は キリスト教用語で、「神の子キリストが十字架にかかって犠牲の死を遂げることによって、人類の罪を償い、救いをもたらしたという教義。」キリスト教とその教義の中心。罪のあがない。
・光焔(こうえん)……①光とほのお。 ②雄大な勢い。
・呵責(かしゃく)…… 叱り責めること。責めさいなむこと。
・利権(りけん)……①鋭利なつるぎ。 ②煩悩を破りくだく仏智をたとえていう語。
・捕縄(ほじょう)……罪人などを捕らえてしばるためのなわ。とりなわ。
第28章 皇統第10代[上代第10代]髙皇産神霊身光天津日嗣天皇
・・・・・ 83
・皇祖皇太神宮(すみおやすみらおおたましいたまや)は、「古事記」「日本書紀」よりもはるか昔の神話(3000億年前からの歴史)が神代文字で記載されている古文書「竹内文書・竹内文献」を受け継ぐ。
第二十九章 第七次神政内閣(大広木正宗大神 定予姫大神)
・・・・・ 85
・事跡(ことと)…… 業績。
・素志(そし)……平素の志。かねての願い。
・義理(ぎり)……① 物事の正しい筋道。また、人として守るべき正しい道。道理。すじ。② 社会生活を営む上で、立場上、また道義として、他人に対して務めたり報いたりしなければならないこと。道義。③ つきあい上しかたなしにする行為。④ 血族でない者が結ぶ血族と同じ関係。血のつながらない親族関係。⑤わけ。意味。
・勘考(かんこう)…… よく考えること。思案。
・廓清(かくせい)…… これまでにつもりたまった悪いことをはらい除いて清めること。粛清。
・肯(がえん)ずる……①…することを肯定しない。…することを承諾しない。②(①の本来の否定の意味が失われて肯定の意味に転じた。打消にはさらに下に否定の助動詞が添えられて、ガエンゼズ・ガエンジナイという形で用いられるようになる)…することを肯定する。…することを承諾する。
・最后(さいご)……最後の。最終の。
第30章 皇統第11代[上代第11代]神皇産霊身光天津日嗣天日天皇
・・・・・ 87
第31章 皇統第12代[上代第12代]宇麻志訶備比古遅身光天津日嗣天皇
・・・・・ 88
・大勇(たいゆう)……まことの勇気。大事に当たって奮い起こす勇気。沈勇。
・更(あらた)めて……今までのものを新しくかえる。とりかえる。
・知食(しろしめ)す……①領有なさる。統治なさる。②知っていらっしゃる。ご存じである。
・勅定(ちょくじょう)……天皇の仰せ。天皇のご命令。勅命。みことのり。
第32章 皇統第13代[上代第13代]天之常男身光天津日嗣天日天皇
・・・・・ 90
・勧農頭(かんのうかしら)……勧農 (かんのう)とは、支配者が 農業 を振興・奨励する民政施策を指す(日本史 の用語)。 日本の 律令 において 国司 の職務とされたのが初見である。 元は中国古典に見られる『勧課農桑』という句が略されたもので、 儒教 的な 農本主義 に基づく言葉であり、秋の「収納」に対し、春の「勧農」という言葉もある。
第33章 皇統第14代[上代第14代]国常立五身光天津日嗣天日天皇
・・・・・ 90
・飛騨位山……岐阜県高山市にある、標高1,529mの山。
・跋扈(ばっこ)……思うままに勝手なふるまいをすること。
・事跡(じせき)…… 物事が行われたあと。事件のあと。事実の痕跡。
第34章 皇統第15代[上代第15代]豊雲野根身光天日嗣天日天皇
・・・・・ 92
第35章 皇統第16代[上代第16代]宇比地煮身光天日嗣天皇
・・・・・ 93
・磨(す)る……①物に、他の物を強く触れ合わせて動かす。こする。②物の表面に他の物を押し付けて繰り返し動かす。③賭事などで、金を使ってなくす。費やす。すり減らす。
・御璽(ぎょじ)……天皇の印章。天皇の行為であることの証明として、法律や政令などの公布文や認証文に押される。玉璽。御印(ぎよいん)。(「御璽(みしるし)」と読む場合は、皇位を示すしるし。三種の神器。特に、玉。)
第36章 皇統第17代[上代第17代]角樴身光天津日嗣天日天皇
・・・・・ 94
・応復し(?)……往復の意味か?
・復命(ふくめい)……命令を受けた者が、その経過や結果を報告すること。復申。
第37章 皇統第18代[上代第18代]大斗能地王身光天津日嗣天日天皇
・・・・・ 95
・親裁(しんさい)……天皇や国王などがみずから裁決を下すこと。
・躬(みずか)ら
・還幸(かんこう)……①天皇が出先から帰ること。還御(かんぎよ)。②神が神幸先から帰ること。
第38章 皇統第19代[上代第19代]面足日子身光天津日嗣天日天皇
・・・・・ 96
第39章 皇統第20代[上代第20代]惶根王身光天津日嗣天日天皇
・・・・・ 96
第40章 第8次神政内閣(桃上彦神 津上姫神)
・・・・・ 97
・万般(ばんぱん)……あらゆる方面。すべての事柄。百般。
・偶像(ぐうぞう)……①木・石・土・金属などで作った像。②神仏をかたどった、信仰の対象となる像。③あこがれや崇拝の対象となるもの。
・施設(しせつ)……①ある目的のために建物などをもうけること。また、その設備。
・傀儡(かいらい)……①あやつり人形。くぐつ。でく。②)自分の意志や主義を表さず、他人の言いなりに動いて利用されている者。でくの坊。
・熄(や)む……①きえる。火がきえる。 ②やむ。やめる。なくなる。
・実(じつ)……①うそ偽りのないこと。真実。本当。②内容。実体。実質。③誠実な気持ち。まごころ。④実際の成績。充実した成果。実績。⑤珠算で、被乗数。または、被除数。
・全(まっと)うする……完全に果たす。完全に終わらせる。
・素心(そし)……平素から抱いている志。以前からもっている希望。
・貫徹(かんてつ)……意志・方針・考え方などを貫き通すこと。最後までくじけずに続けること。
・吾人(ごじん)……①一人称の人代名詞。わたくし。②一人称複数の人代名詞。われわれ。
・如上(じょじょう)……前に述べたとおり。上述。前述。
第41章 皇統第21代[上代第21代]伊邪那岐身光天津日嗣天日天皇
・・・・・ 99
・蘆舟(あしぶね)……イネ科の多年草「葦」は「蘆」「葭」とも書くことから、最も原始的な、葦やイグサなどを束ねて作った小さい舟「葦舟」のこと。
・生国(しょうごく)……うまれた国。出生地。
・途次(とじ)……みちすがら。みちみち。途中。
・大勇(たいゆう)……まことの勇気。大事に当たって奮い起こす勇気。沈勇。
・まします(在す・坐す)……「在ます」の尊敬語。おわします。いらっしゃる。
・物情騒然(ぶつじょうそうぜん)……世の中が騒がしく、今にも何かが起こりそうな様子。
・治定(じじょう、ちてい)……世の中をおさめさだめること。
第42章 皇統第22代[上代第22代]天疎日向津比売身光天津日嗣天日天皇
・・・・・ 102
・治績(ちせき)…… 政治上の功績。
・御諡(ギョシ)……「諡号」( 生前の行いを尊び死後に贈られる称号。おくりな。戒名。)
・誤謬(ごびゅう)……あやまり。間違い。
・位山(くらいやま)……岐阜県北部、高山市・下呂市境にある山。標高1529メートル。
・無極(むごく)……この上もないこと。無上至極。
・羽衣(はごろも)……①鳥の羽で作った薄く軽い衣。天人がこれを着て自由に空中を飛行するという。あまのはごろも。あまごろも。②鳥・虫などの翅。
・拝祝し(はいしゅく?)し……通常、神様や先祖を敬って祝う言葉として使われます。神社や神棚で参拝する際、またはお祝い事の場で神様に感謝や祈願を伝える際に用いられることがあります。(AI回答)
・婦負郡(ねいぐん)……は富山県(越中国)にあった郡。
・暴戻(ぼうれい)……あらあらしく道理にもとること。
・所期(しょき)……期待すること。また、期待するところ。
・禍心(かしん)……他人に災いを加えようとする心。害心。
・専断(せんだん)……自分だけの考えで勝手に物事を決めて行うこと。また、そのさま。
・横暴(おうぼう)……権力や腕力にまかせて無法・乱暴な行いをすること。また、そのさま。
・五声(ごせい)……①中国・日本音楽で、音階を構成する宮・商・角・徴・羽の五つの音。特に、雅楽・声明での用語。五音(ごいん、ごおん)。②五更の第五番目の時刻。戊夜。(戊夜:五夜の一。およそ今の午前3時または4時から2時間をいう。寅の刻。五更。
・五声勢声(ごせいせいせい)……五音の持つ力や勢いを表現する言葉として、五音の持つ影響力や、五音が作り出す音の響きや雰囲気などを表現する際に使われます。
・時を作る……鶏が鳴いて夜明けの時を知らせる。
・出湯(でゆ)……温泉
・湯花(ゆばな)……(=湯の花)鉱泉や温泉の噴き出し口や流路に生じる沈殿物。硫黄(いおう)泉の硫黄、石灰泉の石灰華、珪酸泉の珪華など。温泉華。
・探湯(くかたち、くがたち、くかだち)……古代の裁判における真偽判定法。正邪を判断する場合、神に誓って熱湯の中に手を入れさせ、正の手はただれないが、邪の手はただれるとした。くか。
・檀君(だんくん)……檀君神話とは、朝鮮の建国神話。天孫の檀君が古朝鮮を開き、その始祖になったというもの。檀君は平城に都を開き、1500年間、国を統治したという神話の前半部分は、日本の天孫降臨神話に対応する。
・擾乱(じょうらん)……入り乱れて騒ぐこと。また、秩序をかき乱すこと。騒乱。
・識(し)る……見分ける、知識を得る、認識する、などの意味の表現。
・復命(ふくめい)……命令を受けた者が、その経過や結果を報告すること。復申。
・みそなわす……見る」の尊敬語。ごらんになる。
・入御(にゅうぎょ)……天皇・皇后・皇太后が内裏へはいること。じゅぎょ。
・悪(あく)み……憎み
・罪(つみ)し……「罪す」(罰する。処罰する。)
・体(たい)する……命令や教えなどを心にとどめて守るようにする。
・桎梏(しっこく)……人の行動を厳しく制限して自由を束縛するもの。「桎」は足かせ、「梏」は手かせの意。
・給(たま)う……(=賜う)
[一][動ワ五(ハ四)]《上位から下位に物や恩恵を与える意から、その動作主を敬う語となる。現代では文語的な文章か、特別の堅い言い方でないと尊敬語としては用いない》①「与える」「くれる」の尊敬語。お与えになる。くださる。②人をおよこしになる。③自己側の動作に用い、尊大な語気を表す。目下の者に与える。くれてやる。④特に命令形は、上にくるはずの動詞を略して、命令・勧誘の意を表す。なさい。⑤(補助動詞)動詞・助動詞の連用形に付く。㋐その動作主が恩恵を与えてくださる意を表す。…てくださる。㋑その動作主を尊敬する意を表す。お…になる。お…なさる。㋒尊敬の助動詞「す」「さす」に付いて「せ(させ)たまふ」の形で、程度の強い尊敬の意を表す。㋓同輩以下の者に対し、親しみをこめたりやわらかに命令したりするのに用いる。
[二][動ハ下二](1)「もらう」の意の謙譲語。多く、飲食物の場合に用いる。いただく。頂戴する。㋑(かしこまりあらたまった会話・消息で用いる。平安中期以降の用法)自己または自己側の動作として用いる動詞(主として「思う」「見る」「聞く」)に付いて、聞き手に対してその動作をへりくだる意を表す。…させていただきます。…します。
・冊立(さくりつ)……①中国で、天子が諸侯を封ずること。 ②勅命によって皇太子・皇后を立てること。
・往昔(おうせき)…… 過ぎ去った昔。いにしえ。往古。おうじゃく。
第43章 皇統第23代[上代第23代]天之忍穂耳身光天津日嗣天日天皇
・・・・・ 112
・附会……無理につなぎ合わせること。こじつけること。
・奉捧(ほうぼう)……「奉」は、両手で受ける、おし戴いて大切にする、「捧」は、両手で捧げもつの意。奉捧という語はみつからない。
・御製(ぎょせい)……天皇の作った詩文・和歌。古くは、他の皇族の場合にもいった。おおみうた。
第44章 皇統第24代[上代第24代]天之仁仁杵身光天津日嗣天日天皇
・・・・・ 119
・目次(P25)では「天之仁仁杵身光天津日嗣天日天皇」だが、この章冒頭では、「天日」がない「天之仁仁杵身光天津日嗣天皇」となっている。
・親裁(しんさい)……君主がみずから裁断を下すこと。特に、明治憲法下、天皇の大権に関する政務を天皇みずから裁決すること。
・臨幸(りんこう)…… 天子が行幸して、その場所に臨むこと。
・供奉(ぐぶ)…… ①行幸などの行列に加わること。また、その人。 ②奉仕すること。 ③内供奉の略。
・奏上(そうじょう)……天子に申し上げること。
・産屋(うぶや)…… ①出産のために新たに建てた家。 ②出産のために使う室。
・従容(しょうよう)……動じることなくゆったりとしているさま。おちついたさま。
・戯(たわむれ)…… ①遊び興ずること。遊戯。 ②ふざけること。おどけること。滑稽。冗談。また、本気でなくすること。軽い気持ですること。
・雙……雙(ふた)つ。
・哺育(ほいく)……はぐくみ育てること。動物の子が独立生活を営み得るまで、親が保護・養育すること。
第45章 皇統第25代[上代第25代]天津彦火火出身身光天津日嗣天日天皇
・・・・・ 124
・臨幸(りんこう)…… 天子が行幸して、その場所に臨むこと。
・還幸(かんこう)…… ①天皇が行幸先から帰ること。 ②神が神幸しんこう先から帰ること。
第46章 皇統第26代[葺不合第1代]武巣鵜草葺不合身光天津日嗣天日天皇
・・・・・ 126
・天乞山(あまごいやま)……滋賀県東近江市にある方墳の古墳。
・八咫(やた)……長いこと。また、巨大なこと。(八咫の約。咫は上代の長さの単位で、手のひらの下端から中指の先端までの長さ。一咫は周尺で8寸、約18㎝。一説に、親指と中指とを開いた長さ)
・幄屋……儀式や祭祀などの際、庭上に設けるテントのような仮屋。参列者を入れたり儀式の準備をしたりするところ。
・幔幕(まんまく)……式場・会場などに張りめぐらす幕。上下両端を横幅よこのとし、その間を縦幅として縫い合わせたもの。上端だけ横幅のもの、あるいは縦幅だけで全く横幅を欠くものもある。
・七五三縄(しめなわ)……神前または神事の場に不浄なものの侵入を禁ずる印として張る縄。一般には、新年に門戸に、また、神棚に張る。左捻よりを定式とし、三筋・五筋・七筋と、順次に藁の茎を捻り放して垂れ、その間々に紙垂かみしでを下げる。(=標縄、注連縄)
・夭折(ようせつ)……年若くして死ぬこと。
・私(わたくし)に…… ①公に対し、自分一身に関する事柄。うちうちの事柄。 ②「~に」表ざたにしない事。ひそか。内密。秘密。③自分だけの利益や都合を考えること。ほしいままなこと。自分勝手。
・竜灯(りゅうとう)…… ①海中の燐光が灯火のように連なり現れる現象。 ②神社に奉納する灯籠。
・嘉(よみ)する…… 神や上位の者が、人間や下位の者の言動を褒める。よしとする。
・飫肥……飫肥(おび)は、宮崎県の南部、日南市中央部にある地区。
・上陵……読み「うえのみささぎ」
・斂葬(れんそう)……屍をうずめ、ほうむること。
・連綿(れんめん)……長くひきつづいて絶えないさま。連々。
・関知(かんち)……ある事に関係して知ること。あずかり知ること。多く、下に打消の表現を伴う。
・往昔(おうせき)……過ぎ去ったむかし。いにしえ。往古。おうじゃく。
・纂奪(さんだつ)=簒奪(さんだつ)……本来地位の継承資格が無い者が、帝王の位、政治の実権
などを奪い取ること。簒位。
・専断(せんだん)……自分だけの意見で勝手に物事をとりはからうこと。
・横暴(おうぼう)……わがままで乱暴なこと。
・資(し)する…… ①たすけとする。役立てる。 ②費用を給する。もとでを与える。
第47章 皇統第27代[葺不合第2代]軽島日高日子不合二代身光天津日嗣天日天皇
・・・・・ 131
第48章 皇統第28代[葺不合第3代]真皇真輝彦不合三代天日天皇
・・・・・ 132
・改変……内容を改める。
・神祇(じんぎ)……天神と地祇。天つ神と国つ神。かみがみ。
第49章 皇統第29代[葺不合第4代]玉噛彦天津日嗣不合四代天日天皇
・・・・・ 134
・親裁(しんさい)……君主がみずから裁断を下すこと。特に、明治憲法下、天皇の大権に関する政務を天皇みずから裁決すること。
・瓊矛(ぬほこ)……玉で飾った矛。
・逆矛(さかほこ)……①「天の逆鉾」の略。 ②天の逆鉾に擬して、宮崎県の高千穂峰の頂上に立てられている1丈(約3m)ほどの金属製の逆さのほこ。
第50章 皇統第30代[葺不合第5代]天地明成赤珠彦不合五代天日身光天皇
・・・・・ 134
・改定……従来のきまりなどを改め定めること。
・佩用(はいよう)……勲章・刀剣などを、身につけて用いること。
第51章 皇統第31代[葺不合第6代]石鉾歯並執楯不合六代天日身光天皇
・・・・・ 135
・佩用(はいよう)…… 勲章・刀剣などを、身につけて用いること。
第52章 皇統第32代[葺不合第7代]櫛豊媛不合七代天日身光天皇
・・・・・ 136
・践祚(せんそ)……先帝の崩御あるいは譲位によって、天子の位を受け継ぐこと。
第53章 皇統第33代[葺不合第8代]光徹笑勢媛不合第八代天日身光天皇
・・・・・ 137
第54章 皇統第34代[葺不合第9代]千種媛不合第九代天日身光天皇
・・・・・ 138
第55章 皇統第35代[葺不合第10代]千葦媛不合理第十代天日身光万国棟梁天皇
・・・・・ 138
・幣代(みてぐらしろ)……神に奉る物の総称。ぬさ。御幣。幣帛。
・「大木・小木に餅が出来」(?)……「木(き)に餅(もち)がなる」は、到底ありえないこと、および、ありえないほど話がうますぎることを指す意味で用いられる言い回し。ただ、この箇所の場合、「大木・小木に餅が出来」――大木・小木とある上に、注意を促す「〇〇〇〇」まで付けられていることから、上記の言い回しではないと思われる。
第56章 皇統第36代[葺不合第11代]禍斬剣彦不合十一代天日身光万国棟梁天皇
・・・・・ 139
・行在(あんざい)……「(「行在所=行宮」(=「皇の行幸のときに旅先に設けた仮宮」)であることから)、
から、「仮住まい」の意味と思われる。
第57章 皇統第37代[葺不合第12代]弥広殿作不合十二代天日身光天皇
・・・・・ 141
第58章 皇統第38代[葺不合第13代]豊明国押彦不合十三代天日身光天皇
・・・・・ 142
第59章 皇統第39代[葺不合第14代]火之進奇猿媛不合十四代天日身光天皇
・・・・・ 142
・こよなく……この上なく。古くは単に程度のはなはだしいことを表したが、現代では文語的な表現として賛美の情感を伴って用いられる。
第60章 皇統第40代[葺不合第15代]臼杵不合十五代天日身光天皇
・・・・・ 144
第61章 皇統第41代[葺不合第16代]産門真幸不合十六代天日身光天皇
・・・・・ 144
第62章 皇統第42代[葺不合第17代]表照明媛不合十七代天日身光天皇
・・・・・ 145
第63章 皇統第43代[葺不合第18代]俵細里媛不合十八代天日身光天皇
・・・・・ 146
第64章 皇統第44代[葺不合第19代]少名形男彦不合十九代天日身光天皇
・・・・・ 146
・尺(しゃく)・・・・‥ ①尺貫法における長さの単位。古来用いられ、さまざまあったが、明治以後は1mの33分の10と定義された。寸の10倍、丈の10分の1。 ②ながさ。たけ。「―が足りない」 ③ものさし。さし。
・大力(だいりき)……強力。怪力。
第65章 皇統第45代[葺不合第20代]天津明少大汝彦不合二十代天日身光天皇
・・・・・ 146
第66章 皇統第46代[葺不合第21代]天饟明立不合二十一代天日身光天皇
・・・・・ 147
第67章 皇統第47代[葺不合第22代]天明開神魂彦不合二十二代天日身光天皇
・・・・・ 148
第68章 皇統第48代[葺不合第23代]天饟国饟狭真部国葦不合二十三代天日身光天皇
・・・・・ 148
第69章 皇統第49代[葺不合第24代]天饟国饟黒浜彦不合二十四代天日身光天皇
・・・・・ 150
第70章 皇統第50代[葺不合第25代]富秋足中置不合二十五代天日身光天皇
・・・・・ 150
・復命(ふくめい)……命を受けて事を処理したものが、その経過や結末を上申すること。かえりもうし。復申。
第71章 皇統第51代[葺不合第26代]種淅彦不合二十六代天日身光天皇
・・・・・ 150
第72章 皇統第52代[葺不合第27代]建玉彦不合二十七代天日身光天皇
・・・・・ 151
第73章 皇統第53代[葺不合第28代]天之海童及噱楽之雄不合二十八代天日身光天皇
・・・・・ 151
第74章 皇統第54代[葺不合第29代]神豊実媛不合二十九代天日身光天皇
・・・・・ 152
第75章 皇統第55代[葺不合第30代]円背之男不合三十代天日身光天皇
・・・・・ 152
第76章 皇統第56代[葺不合第31代]橘媛不合三十一代天日身光天皇
・・・・・ 153
第77章 皇統第57代[葺不合第32代]花撰媛不合三十二代天日身光天皇
・・・・・ 153
第78章 皇統第58代[葺不合第33代]清之宮媛不合三十三代天日身光天皇
・・・・・ 154
第79章 皇統第59代[葺不合第34代]八千尾亀之男不合三十四代天日身光天皇
・・・・・ 154
第80章 皇統第60代[葺不合第35代]花媛不合三十五代天日身光天皇
・・・・・ 155
第81章 皇統第61代[葺不合第36代]若照彦不合三十六代天日身光天皇
・・・・・ 155
第82章 皇統第62代[葺不合第37代]松照彦不合三十七代天日身光天皇
・・・・・ 156
第83章 皇統第63代[葺不合第38代]天津太祝詞調子不合三十八代天日身光天皇
・・・・・ 156
・諮(はか)る……①数える。計算する。②はかり・ます・ものさしで、重さ・量・長さを知ろうと試みる。見つもる。考える。分別する。考慮する。②物事の内容・程度を推しはかる。③予測する。
第84章 皇統第64代[葺不合第39代]神足伊足彦不合三十九代天日身光天皇
・・・・・ 157
第85章 皇統第65代[葺不合第40代]神楯媛不合四十代天日身光天皇
・・・・・ 157
・奉祭(ほうさい)……神仏などをまつること。「奉斎」は、神仏などを慎んでまつること。身を清めてまつること。
第86章 皇統第66代[葺不合第41代]神楯広幡八十足彦不合四十一代天日身光天皇
・・・・・ 158
第87章 皇統第67代[葺不合第42代]鶴舞媛不合四十二代天日身光天皇
・・・・・ 158
第88章 皇統第68代[葺不合第43代]豊足大御中不合四十三代天日身光天皇
・・・・・ 159
第89章 皇統第69代[葺不合第44代]大炊気吹不合四十四代天日身光天皇
・・・・・ 159
第90章 皇統第70代[葺不合第45代]空津争鳥不合四十五代天日嗣天皇
・・・・・ 159
第91章 皇統第71代[葺不合第46代]不合四十六代天日嗣天皇
・・・・・ 160
第92章 皇統第72代[葺不合第47代]大庭足媛不合四十七代天日嗣天皇
・・・・・ 161
第93章 皇統第73代[葺不合第48代]豊津神足別不合四十八代天日嗣天皇
・・・・・ 161
第94章 皇統第74代[葺不合第49代]豊足彦不合四十九代天日嗣天皇
・・・・・ 162
第95章 皇統第75代[葺不合第50代]神足別国神之女不合五十代天日嗣天皇
・・・・・ 162
第96章 皇統第76代[葺不合第51代]国押別足日不合五十一代天日嗣天皇
・・・・・ 163
・仙洞(せんとう)…… ①仙人の居所。 ②太上天皇(上皇)の御所。院の御所。かすみのほら。はこやのやま。仙院。 ③太上天皇の称。
第97章 皇統第77代[葺不合第52代]天津紅之枝不合五十二代天日嗣天皇
・・・・・ 163
第98章 皇統第78代[葺不合第53代]天開明知国東不合五十三代天日嗣天皇
・・・・・ 164
第99章 皇統第79代[葺不合第54代]髙天原輝徹国知不合五十四代天日嗣天皇
・・・・・ 164
第100章 皇統第80代[葺不合第55代]天津玉拍彦不合五十五代天日嗣天皇
・・・・・ 164
第101章 皇統第81代[葺不合第56代]天津成瀬男不合五十六代天日嗣天皇
・・・・・ 165
★――★――★――Ⅱ巻――★――★――★
第102章 皇統第82代[葺不合第57代]天津照雄之男不合五十七代天日嗣天皇
・・・・・ 166
第103章 皇統第83代[葺不合第58代]御中主幸玉不合五十八代天日嗣天皇
・・・・・ 166
第104章 皇統第84代[葺不合第59代]天地明玉主照不合五十九代天日嗣天皇
・・・・・ 170
第105章 神社の祭祀
・・・・・ 171
第106章 葬祭
・・・・・ 173
・見当(みあ)たる……さがしていたものが見つかる。
・天然(てんねん)……①人為が加わっていないこと。自然のままであること。また、そのさま。②うまれつき。天性。
・顕世(げんせ)……現世。(「顕界(げんかい)」は、この世。現世。⇔ 幽界)
・安全(あんぜん)……危険がなく安心なこと。傷病などの生命にかかわる心配、物の盗難・破損などの心配のないこと。また、そのさま。
・言勝(いいがち)……① 負けじと盛んに言うこと。われがちにしゃべりまくること。② とかく口にすること。ともすると言い出すこと。
・和合(わごう)……①仲よくなること。親しみ合うこと。②男女が結ばれること。結婚すること。③まぜ合わせること。調合。また、まじり合うこと。
・天職(てんしょく)……①天から授かった職業。また、その人の天性に最も合った職業。②天子が国家を統治する職務。③遊女の等級の一。大夫の次の位。天神。
・霊遷(れいせん)……「遷霊際(せんれいさい)」は、故人の魂を遺体から「霊璽(れいじ) 」に移すための儀式で、「通夜祭(つやさい)」の中で行われる。「霊璽」は、神道で使用する仏式の位牌にあたるもの。
第107章 世界再統一の神勅
・・・・・ 177
・棟梁(とうりょう)……①建物の棟(むね)と梁(はり)。②㋐一族・一門の統率者。集団のかしら。頭領。また、一国を支える重職。㋑仏法を守り広める重要な地位。また、その人。㋒大工の親方。
・覊絆(きはん)……足手まといとなる身辺の物事。きずな。ほだし。
・恣(ほしいまま)……思いのままに振る舞うさま。自分のしたいようにするさま。
・論(ろん)を俟(ま)たない……言うまでもない、ことさらに述べ立てるまでもない、
・大変(たいへん)……①重大な事件。大変事。一大事。②物事が重大であること。また、そのさま。③苦労などが並々でないこと。また、そのさま。
・申政(しんせい)……主に歴史的な文脈で使われる言葉で、特に摂関政治における公卿の議決(陣定)や、天皇に事に関する報告(申文)などの文脈で用いられます。具体的には、公卿が天皇に建議したり、官庁からの日常的な事項や人事に関する内容を報告する際に使われます。(AI回答)
・霊験(れいげん)……人の祈請に応じて神仏などが示す霊妙不可思議な力の現れ。利益(りやく)。
・無極(むきょく)……①果てがないこと。限りのないこと。また、そのさま。無窮。②電極または磁極が存在しないこと。③人知を越えた果てしないところ。転じて、宇宙の根源のこと。
・天賦(てんぶ)……天から賦与されたもの。生まれつきの資質。
・天質(てんしつ)…… 生まれつきの性質。天性。
・陪(ばい)……①そばに付き添う。伴をする。②補佐する。③家来の家来。
・欠礼(けつれい)……礼儀を欠くこと。あいさつをしないこと。失礼。
・禍……「か」=災い。ふしあわせ。「まが」=よくないこと。悪いこと。わざわい。
第108章 見守り神文字
・・・・・ 185
第109章 皇統第85代[葺不合第60代]天照櫛豊媛不合六十代天日嗣天皇
・・・・・ 187
第110章 皇統第86代[葺不合第61代]豊足日明媛不合六十一代天日嗣天皇
・・・・・ 188
第111章 皇統第87代[葺不合第62代]天豊足別彦不合六十二代天日嗣天皇
・・・・・ 188
第112章 皇統第88代[葺不合第63代]事代国守髙彦系不合六十三代天日嗣天皇
・・・・・ 189
第113章 皇統第89代[葺不合第64代]豊日足彦不合六十四代天日嗣天皇
・・・・・ 190
第114章 皇統第90代[葺不合第65代]勝勝雄之男不合六十五代天日嗣天皇
・・・・・ 190
第115章 皇統第91代[葺不合第66代]豊柏木幸手男不合六十六代天日嗣天皇
・・・・・ 191
第116章 言語文字の教伝
・・・・・ 191
・幾何(いくばく)…… ①どれほど。どんなに多く。 ②(「も」を伴い、否定・反語に用いる)なにほども。
第117章 古代文字
・・・・・ 198
・虚妄(きょぼう、きょもう、こもう)……うそ。そらごと。うそいつわり。
・所説(しょせつ)…… 説くところ。意見・主張の内容。説。
・呶々論駁……呶呶(どど):やかましく言うさま。くどくどしく言うさま。論駁(ろんばく):相手から加えられた意見に対抗して論じかえすこと。
第118章 皇統第92代[葺不合第67代]春建日媛不合六十七代天日嗣天皇
・・・・・ 202
第119章 皇統第93代[葺不合第68代]天津日高日子宗像彦不合六十八代天日嗣天皇
・・・・・ 203
第120章 皇統第94代[葺不合第69代]神足別豊![]() 不合六十九代天日嗣天皇
不合六十九代天日嗣天皇
・・・・・ 203
・現在(げんざい)……現存すること。
・彷彿(ほうふつ)…… ①よく似ているさま。ありありと思い浮かぶさま。 ②はっきりと識別できないさま。ぼんやり見えるさま。ほのか。かすか。
・薨(こう)……貴人が亡くなる。諸侯が死ぬ。みまかる。
第121章 日本中古文明[葺不合朝文化]の履滅
・・・・・ 205
・半(なか)ば過ぎ……全体のだいたい半分を過ぎたあたり、を指す表現。
・精細(せいさい)……くわしくこまかいこと。詳細。
・没却(ぼっきゃく)……なくすること。無視すること。
第122章 万国大地変
・・・・・ 206
・由(よし)なし……①理由がない。根拠がない。②方法がない。手段がない。③つまらない。とりとめがない。くだらない。無意味だ。④関係がない。縁がない。
・島嶼(とうしょ)……しま。島々。
・遺跡(いせき)……①貝塚・古墳・集落跡など、過去の人類の生活・活動のあと。遺物・遺構のある場所。②昔の建物や歴史的事件などのあった場所。旧跡。古跡。③先人ののこした領地・官職など。また、その相
・「木(き)に餅(もち)がなる」……到底ありえないこと、および、ありえないほど話がうますぎることを指す意味で用いられる言い回し。
・片鱗(へんりん)……①一枚のうろこ。②多くの中のほんの少しの部分。一端。
・覗(うかが)い知(し)る……すでにわかっていることをもとにして推測し、そのあらましを知る。だいたいの見当をつける。(「窺う」と「覗う」の用法は近く、相手の様子をひそかに見る時に使う)
・延(ひ)いては……[副]「ひいて」の強めた言い方。「ひいて」は、「ある事だけにとどまらず、さらに進んで。それが原因となって、その結果。」の意。
・淵源(えんげん)…… 物事の起こり基づくところ。根源。みなもと。
・希臘(ぎりしゃ)……ギリシャ。正称、ギリシャ共和国。
・散見(さんけん)……あちこちに見えること。ちらほら目につくこと。
・須臾(しゅゆ)……短い時間。しばらくの間。ほんの少しの間。
・煙滅(えんめつ)……(「湮滅(いんめつ)」の誤りから)跡形もなく消えてなくなること。
・夢想(むそう)……①夢の中で思うこと。夢に見ること。②夢のようにあてもないことを想像すること。空想すること。③夢の中に神仏が現れて教えを示すこと。
第123章 国素国万造主大神三千年の仕組
・・・・・ 223
・一朝(いっちょう)……①ある朝。ある日。②わずかな間。③朝廷全体。また、朝廷に仕えるすべての人。
・桑滄(そうそう)の変(へん)……世の中の移り変わりが激しいことのたとえ。(「滄桑之変」が正しいが――「滄桑」は、大きな海と桑畑のことから、大海が桑畑に、または桑畑が大海になるような変化が起こるとの意――「滄」の代りに「桑」を使っていると思われる)
・弥(いや)が上にも……「さらに」「いっそう」「ますます」という意味で使われる。それでなくとも顕著だった傾向が、より一層はなはだしくなった、という状況を表現する意味合いを示す。
・鋭意(えいい)……気持ちを集中して励むこと。専心。
第124章 皇統第95代[葺不合第70代]神心伝物部建不合七十代天日嗣天皇
・・・・・ 224
第125章 皇統第96代[葺不合第71代]天照国照日子百日臼杵不合七十一代天日嗣天皇
・・・・・ 224
第126章 皇統第97代[葺不合第72代]彦五瀬不合七十二代天日嗣天皇
・・・・・ 226
・東遷(とうせん)……都などが東の方へうつること。
第127章 神武紀元の真意義
・・・・・ 226
・傾注(けいちゅう)……精神や力を一つの事に集中すること。
・扶植(ふしょく)……勢力などを、植えつけ拡大すること。
・奮然蹶起……奮然(ふんぜん)ふるいたつさま。/蹶起(けっき)思いきって立ち上がること。決然と行動を起こすこと。
・興深(きょうふか)げ……興味深げ。
・途次(とじ)……みちすがら。みちみち。途中。
・昏睡(こんすい)……①前後不覚にねむること。②意識障害のうち最も高度なもので,刺激に対する反応がまったくみられない状態。
・夢寐(むび)…… 眠って夢を見ること。眠ること。また,その間。
・叛乱(はんらん)……支配体制や上からの統率にそむいて乱を起こすこと。反乱。
・醒(さ)める……①眠っている状態から、意識のはっきりした状態に戻る。②眠けや酒の酔いが消える。③心をとらえていた迷いがなくなる。正気をとりもどす。冷静になる。
・稽(かんが)うる……かんがえる・ とどめる・ とどこおる
・虚妄(きょもう)……事実でないこと。うそいつわり。うそ。こもう。
・想到(そうとう)……考えが及ぶこと。考えつくこと。
・首肯(しゅこう)……うなずくこと。もっともだと納得すること。
・差違(さい)……ほかの元との違い。差異。
・杜撰(ずさん)……①著作で、典拠などが不確かで、いい加減なこと。 ②物事の仕方がぞんざいで、手落ちが多いこと。
・御意(ぎょい)……①貴人や目上の人などを敬って、その考え・意向をいう語。お心。おぼしめし。②目上の人に対して、同意・肯定を示す返事の言葉。ごもっとも。おっしゃるとおり。
・曠し……むなしくする。無駄にする。
・受祚……「祚」は、天子の位、皇位、皇祚、宝祚、たかみくらの意味。受祚は、その祚を受けること。
・大礼(たいれい)……①国家・朝廷の重大な儀式。特に、即位の儀式。大典。②人の一生の中で最も重要な礼式。
・奉持(ほうじ)…… ささげ持つこと。また、いただき奉ること。
・遙拝(ようはい)…… 遠くへだたった所から、神仏などをはるかに拝むこと。
・分明(ぶんめい)……①他との区別がはっきりしていること。あきらかなこと。また、そのさま。②明らかになること。
・画期(かっき)…… 過去と新しい時代とを分けること。また、その区切り。
・至当(しとう)……きわめて当然であり、適切であること。きわめて妥当であること。また、そのさま。
第128章 皇統第98代[葺不合第73代]狭野不合七十三代天日嗣天皇」
[神倭第1代]神日本磐余彦天皇[神武天皇]
・・・・・ 233
・僅々(きんきん)……ごくわずかであるさま。
・勇躍(ゆうやく)……いさみ立ち、心がおどること。
・儒道(じゅどう)……①儒学または儒教の道。②儒教と道教。
・営繕(えいぜん)……建造物を造ったり修理したりすること。
・統理(とうり)……統一しておさめること。
・放擲(ほうてき)……投げ出すこと。捨ててかえりみないこと。
・吾人(ごじん)……①わたくし。②われわれ。
第129章 大広木正宗大神の各宗教樹立
・・・・・ 235
・跳梁(ちょうりょう)……はねまわること。転じて、好ましくないものが、のさばりはびこること。
・専(もっぱら)に……ひたすら~をする。~に専心する。もっぱらとする。
・裔孫(えいそん)…… 遠い子孫。末裔。後裔。子や孫よりもあとの血筋。
・幽玄(ゆうげん)……①物事の趣が奥深くはかりしれないこと。また、そのさま。②中世の文学・芸能における美的理念の一。㋐歌論などで、優艶を基調として、奥深い静寂な余情、象徴的な情調のあること。㋑能楽論で、優雅で柔和な美しさ。美女・美少年などの優美さや、また、寂びた優美さをいう。
・正道(せいどう)……正しい道理。正しい道。また、正しい行為。
・訓(おし)えて……おしえる 。みちびく。
・厳粛(げんしゅく)……①おごそかで、心が引き締まるさま。②まじめで、きびしいさま。真剣なさま。③重大で動かしがたいさま。
・濶達(かったつ)……度量がひろく、物事にこだわらないこと。こせこせしないこと。(=闊達(かったつ))。「闊」は表外字、「濶」は「闊」の異字体。
・随時(ずいじ)……①適宜な時に行うさま。その時々。②日時に制限のないさま。好きな時にいつでも。
・猶太(ゆだや)……広義にはパレスチナ全土、狭義にはパレスチナ中部のエルサレムを中心とする古代ユダ王国の地。ユデア。→イスラエル→パレスチナ。
第130章 近世仏魔の侵入
・・・・・ 239
・淳正(じゅんせい)……かざりけがなく正しいこと。また、そのさま。
・蟠踞(ばんきょ)……①根を張って動かないこと。わだかまること。②その地方一帯に勢力を張っていること。
・素志(そし)……平素の志。かねての願い。
・鳳輦(ほうれん)……①屋形の上に金銅の鳳凰をつけた輿。即位・大嘗会など晴の儀式の行幸に際しての天皇の乗物。②天皇の乗物の美称。
・畏くも(かしこくも)……もったいなくも。おそれ多くも。
・天璽(てんじ)……天皇のしるしとして、歴代に伝える重宝。あまつしるし(天つ印・天つ璽/天つ神の子孫としての証拠。また、皇位のしるし)
・諸般(しょはん)……いろいろの事柄。さまざま。種々。
第131章 皇統第105代[神倭第8代]大日本根子彦国牽天皇(孝元天皇)
・・・・・ 238
第132章 皇統第107代[神倭第10代]御間城入彦五十瓊殖天皇(崇神天皇)
・・・・・ 239
・調伏(ちょうぶく)……①心身をととのえて、悪行を制すること。祈祷によって悪魔・怨敵を下すこと。降伏(ごうぶく)。②まじないによって人をのろい殺すこと。
・聖意(せいい)……①聖人の考え。②天子の考え。
第133章 皇統第108代[神倭第11代]活日入彦五十狭茅天皇
・・・・・ 239
第134章 皇統第111代[神倭第14代]足仲孝天皇(仲哀天皇)
・・・・・ 240
第135章 皇統第112代[神倭第15代]息長帶媛天皇
・・・・・ 241
第136章 皇統第113代[神倭第16代]誉田天皇(応身天皇)
・・・・・ 241
第137章 神宝の秘蔵
・・・・・ 241
・遷(うつ)し
・流離(さすら)う……あてもなく、また、定まった目的もなく歩きまわる。漂泊する。流浪する。
・晨(あした)……朝
・興(おこ)す……「起こす」と同語源
・煬る……①あぶる。やく。火でかわかす。 ②火をもやす。 ③とかす。金属を熱してとかす。
・請罪(?)……勇気をもって謝罪する
・神祇(じんぎ)……天神地祇(天の神と地の神)の略。天神は「あまつかみ」とよび、天上で生まれ、あるいは天上から降った神。地祇は「くにつかみ」とよび、地上に天降った神の子孫、あるいは地上で生まれた神をいう。「令義解」では、天神として伊勢、山城鴨、住吉など、地祇として大神、大倭、葛城鴨などをあげている。
・然(しか)れども……そうだけれども。しかしながら。
・託(かこつ)ける……かこつけること。口実。
・倭(わ)……日本人の住む国。日本のもの。古代、中国から日本を呼んだ名。
・笠縫邑(かさぬいのむら)……日本書紀で、崇神天皇が天照大神を皇女・豊鍬入姫に祭らせたと伝える倭の地。奈良県磯城郡田原本町新木、桜井市内などの説がある。
・仍(よ)りて……それだから。したがって。よって。
・磯城(しき)神……磯城瑞籬宮は、奈良県桜井市金屋にあったとされる崇神天皇の皇居。そのことから、磯城神は、その宮の神?
・棟梁(とうりょう)……①建物の棟と梁。②㋐一族・一門の統率者。集団のかしら。頭領。また、一国を支える重職。㋑仏法を守り広める重要な地位。また、その人。㋒大工の親方。
・暁(さと)る……はっきりと知る。(「悟る」は「迷いが開けて真理を会得する」という意味で使う。「自分の運命を悟る」/「覚る」は「気が付く」「感づく」という意味で使う。「危険を覚る」「死期を覚る」)
・能(よ)く……①念を入れてするさま。②非常に。たいそう。③巧みに。うまく。④本当にまあ。よくぞ。⑤よくもまあ。
・相伝(そうでん)……代々受け継いで伝えること。
・親祭(しんさい)……天皇がみずから神を祭ること。
・慮(おもんばか)る……周囲の状況などをよくよく考える。思いめぐらす。
第138章 古事記の由来
・・・・・ 247
・相伝え(?)……代々受け継いで伝えること。
・胚胎(はいたい)……①みごもること。はらむこと。②物事の起こる原因やきざしが生じること。
・骨幹(こっかん)……①からだの骨組み。骨格。管状骨の骨端以外の主要部。②物事の、かなめとなる部分。根幹。
・齟齬(そご)……物事がうまくかみ合わないこと。食い違うこと。ゆきちがい。
・附会(ふかい)……こじつけること。無理に関係づけること。
・蹈晦(?)……近い字として「韜晦(とうかい)」は、 ①自分の本心や才能、地位などをつつみ隠すこと。②身を隠すこと。姿をくらますこと。
・杜撰(ずさん)……①著作で、典拠などが不確かで、いい加減なこと。 ②物事の仕方がぞんざいで、手落ちが多いこと。
・誤謬(ごびゅう)……まちがえること。まちがい。
・矛盾(むじゅん)……①矛と盾。②二つの物事がくいちがっていて、つじつまが合わないこと。自家撞着。
・一顧(いっこ)……ちょっと振り返って見ること。ちょっと心にとめてみること。一考。
・形而上(けいじじょう)……①形をもっていないもの。②哲学で、時間・空間の形式を制約とする感性を介した経験によっては認識できないもの。超自然的、理念的なもの。
・稽(かんがえ)る……身体が覚えるまで何度も繰り返すのが、稽古。対象は古いもの。その過程が稽る(かんがえる)こと。 考えることも同じ。
・延(ひ)いて……①ある事だけにとどまらず、さらに進んで。それが原因となって、その結果。
・演繹(えんえき)…… ①意義を推し拡げて説明すること。 ②一定の前提から論理規則に基づいて必然的に結論を導き出すこと。通常は普遍的命題(公理)から個別的命題(定理)を導く形をとる。
第139章 三代神勅の真起源
・・・・・ 250
・真個(しんこ)……真実であること。まこと。
・皇孫就而治焉(すめみま、いでましてしらせ)……天孫降臨の際に天照大御神が瓊瓊杵尊にお授けになった神勅の一つで、現代語訳すると「汝、皇孫よ、行って治めなさい」という意味です。この言葉は、天孫が地上に降りて日本の国を治めることを意味しており、天皇の権威と統治の始まりを象徴しています。(AI回答)
・天壊無窮(てんじょうむきゅう)……天地とともに永遠に極まりなく続くさま。「天壌」は天と地。「無窮」は極まりないさま、永遠の意。
・仙洞(せんとう)……①仙人の住む所。②上皇の御所。転じて、上皇。仙洞御所。仙院。
・親裁(しんさい)……君主がみずから裁断を下すこと。
・按(あん)ずるに……思うに。多く自分の考えを述べるとき、冒頭に用いる。
・来来(らいらい)……時などを表す名詞の上に付いて複合語をつくり、「次の次」の意を表す。
・方り……為すにあたりて、 するにあたって
・磐境(いわさか)……神の鎮座する施設・区域。
・彷彿(ほうふつ)……①ありありと想像すること。よく似ているものを見て、そのものを思い浮かべること。②ぼんやりしていること。③よく似ているさま。
・余(あまり)……①余剰。②割り算で割り切れずに残った数。「余りに(形動)」は、①程度のはなはだしいさま。予想を超えているさま。②話にならないほど度が過ぎてひどいさま。あんまり。
・冊立(さくりつ)……勅命によって皇太子・皇后などを正式に定めること。さくりゅう。
・鵺(ぬえ)……①トラツグミの異称。②源頼政が紫宸殿上で射取ったという伝説上の怪獣。頭は猿、胴は狸、尾は蛇、手足は虎に、声はトラツグミに似ていたという。③転じて、正体不明の人物やあいまいな態度にいう。……「鵺式」は、③より「あいまいな」の意味か?
・憶測(おくそく)…… 確かな根拠もなくいいかげんに推測すること。
・あげつら(論)う……物事の理非、可否を論じ立てる。また、ささいな非などを取り立てて大げさに言う。
・言挙(ことあ)げ……ことさら言葉に出して言いたてること。揚言。
・首肯(しゅこう)……うなずくこと。もっともだと納得すること。
第140章 皇統第131代[神倭第34代]豊御食炊事屋比売天皇(推古天皇)
・・・・・ 261
・皮相(ひそう)……①うわべ。表面。 ②真相をきわめず、表面のみを見て下す浅薄な判断。
・陽(よう)に……うわべでは。表面では。また、 公然と。
・陰(いん)に……かげで。内々。
第141章 皇統第136代[神倭第39代]天智天皇
・・・・・ 262
・素服(そふく)……本来は飾り気のない凶服の一種で、染めない素地のままの麻の布などが用いられた。①白地の衣服。 ②喪服。鈍色・黒色に作る。
・奠(さだ)める……①まつる。神仏に酒食などを供える。 ②そなえる。そなえもの。 ③さだめる。位置を決める。
第142章 皇統第137代[神倭第40代]弘文天皇
・・・・・ 262
第143章 皇統第138代[神倭第41代]天武天皇
・・・・・ 262
・勅許(ちょっきょ)……①天子の許可。勅命による免許。②明治憲法下で皇室の重大事項の実行に関し、皇族会議または輔弼機関によらず、天皇の親裁に基づく許可。
・綱領(こうりょう)……①物事の大切なところ。眼目。 ②政党・労働組合などの団体の立場・目的・計画・方針または運動の順序・規範などを要約して列挙したもの。
第144章 皇統第140代[神倭第43三代]文武天皇
・・・・・ 263
・大峰山(おおみねさん)……女人禁制の修行の御山「大峰山」は、山の名称としては、大峰山脈(大峰連峰)山上ヶ岳。山上ヶ岳以外の大峰山脈の山々は、女人禁制を解かれているが、総称として「大峰山」と呼ばれている。大峰山の麓の宿場町・洞川には、大峰山護持院(五ヶ寺)の一寺、龍泉寺が在り、吉野には、金峯山寺や大峰山護持院が在る。
・一言主神(ひとことぬしのかみ)……役行者が葛城山(かつらぎさん)と吉野の金峯山に橋を架けようとした時、 それを手伝った一言主神は容貌を恥じて夜だけ働き、夜明け前に姿を隠したという。
・鋭鋒(えいほう)……①鋭い矛先。②言葉や文章による鋭い攻撃。
・登仙(とうせん)……①仙人となって天にのぼること。 ②貴人の死去の尊敬語。上僊。
・行衛(ぎょえ)……① 行くべき方向。向かっていく先。② 行った方向。 行った先。③今後のなりゆき。また、 将来。前途。
第145章 皇統第141代[神倭第44代]元明天皇
・・・・・ 264
・目(もく)する……①認める。判断する。②注目する。③目で知らせる。目くばせする。
・察知(さっち)……推測して知る。
第146章 皇統143代[神倭第46代]聖武天皇
・・・・・ 264
・三宝(さんぼう)の奴(やっこ)……仏・法・僧の三宝に供養するため、身を捨ててその奴隷となること。
・毘盧舎那仏(びるしゃなぶつ)……大乗仏教における仏の1つ。華厳経では中心的な存在として扱われる尊格で、密教においては大日如来と同一視される。 尊名は華厳経では「舎」の字を用いて毘盧舎那仏。
・散逸(さんいつ)……まとまっていた書物・文献などが散りうせること。
・兵燹(へいせん)……「戦争のために起こる火事。兵火。「燹」は野火の意。
・烏有(うゆう)に帰す…… 何もかもがなくなること。特に、火事で丸焼けになること。
・須(もち)いる……
・威(い)を振(ふ)るう……勢威を示す。「勢威」は、権勢と威力。盛んな勢い。
第147章 皇統第148代[神倭第51代]桓武天皇
・・・・・ 265
・奠(さだ)める……①まつる。神仏に酒食などを供える。 ②そなえる。そなえもの。 ③さだめる。位置を決める。
・皇城(こうじょう)……天子の居住する城。皇居。宮城。
・追(お)う……①先を進むもののあとからついて行く。②目標をめざして進む。③強制してその場・地位などから去らせる。
・不開門(あかずのもん)……平安京大内裏外部門の一つで、一条大通りに通じる北面中央の偉鑒門の異称。不明門とも書く。さらに一般化し、特別の場合にのみ開いて使用する門の意味にも用いる。
・愚弄(ぐろう)……馬鹿にしてからかうこと。
・閉塞(へいそく)……閉じてふさぐこと。ある部分をふさいで他の部分との連絡を断つこと。
第148章 皇統第150代[神倭第53代]嵯峨天皇
・・・・・ 266
・籍(か)りる
第149章 皇統第154代[神倭第57代]清和天皇
・・・・・ 266
・勅使(ちょくし)…… 勅旨を伝達するために派遣される特使。
・総帥(そうすい)……組織全体を指揮する人。本来は、全軍を指揮する人を意味する。
・威風(いふう)…… 威光・威厳のある様子。
・津々浦々(つつうらうら)……いたるところの津や浦。あまねく全国。つづうらうら。
・望(のぞ)む……①遠くからながめやる。 ②願う。欲する。期待する。 ③仰ぐ。慕う。
・素地(そじ)……さらに手を加えて仕上げるもととなるもの。したじ。土台。基礎。
・扶植(ふしょく)……①うえつけること。②たすけたてること。扶持すること。
・掌握(しょうあく)……手のひらの中に握ること。手に入れること。わがものとすること。
・成就(じょうじゅ)……できあがること。なしとげること。成功。達成。
第150章 皇統第158代[神倭第61代]醍醐天皇
・・・・・ 267
・再考(さいこう)……もう一度よく考えること。考えなおすこと。
・興(おこ)る……盛んになる。
・延喜式延喜格(えんぎしきえんぎきゃく)……「延喜」は平安前期、醍醐天皇朝の年号。「延喜式」は、弘仁式・貞観式の後をうけて編修された律令の施行細則。平安初期の禁中の年中儀式や制度などを漢文で記した50巻。「延喜格」は、弘仁格・貞観格の後をうけて、869年(貞観11)から907年(延喜7)に至る格(追加法令)を集めた12巻。現存しない。
・衰微(すいび)……衰えてかすかになること。盛んでなくなること。
・説破(せっぱ)……他の説を言い負かすこと。ときやぶること。ときふせること。論破。
・無慮(むりょ)……およそ。ざっと。大方。あらまし。ぶりょ。
第151章 皇統第160代[神倭第63代]村上天皇
・・・・・ 267
・内裡(だいり)……天皇の住居としての御殿。御所。皇居。禁裏。禁中。
・怨嗟(えんさ)…‥うらみなげくこと。
・褒賞(ほうしょう)……①ほめること。ほめたたえること。 ②ほめる意を表すために与える品。褒美。
・使嗾(しそう)……指図してそそのかすこと。けしかけること。指嗾。
・図(はか)る……意図する。
・「一将功成りて万骨枯る」(いっしょうこうなりてばんこつかる)……ひとりの輝かしい功績の陰には、それを支えたたくさんの人の努力や犠牲があるということ。「万骨」には「多くの人の骨」の他、「たくさんの犠牲」という意味もある。
・私(わたくし)する…… 公のものを自分のもののように勝手にする。
・御稜威(みいつ)……天皇・神などの威光。強い御威勢。
・安(やす)んずる…… ①安らかになる。平安になる。安心する。 ②それに満足して不満に思わない。甘んずる。 安らかにする。安泰にする。
・玉體(ぎょくたい)……①玉のように美しいからだ。 ②天子または貴人のからだ。③他人を敬って、そのからだをいう語。
・阿倍晴明(あべのせいめい)……安倍晴明(921〜1005)。平安中期の陰陽家。よく識神しきがみを使い、あらゆることを未然に知ったと伝えられる。伝説が多い。
第152章 皇統第170代[神倭第73代]白河天皇
・・・・・ 268
・延暦寺と円城寺の僧徒の戦い……始まりは、同じ天台宗内での思想が2つに分かれたことが原因。
天台宗の開祖「最澄」は唐で学んだ「天台宗」の教えを伝え、空海は「真言宗」という形で密教を伝えた。朝廷が密教を選んだため、天台宗は下火となる。天台宗は最澄の死後、天台宗と密教の完全なる融合を目指すこととなり、3代目天台宗トップ・円仁(794年〜864年)、5代目トップ・円珍(814年〜891年)が推進する。ところが、2人の思想には、密教に対して決定的な考え方の違いがあった。円仁は、天台宗で最も重要視されていた経典「法華経」の教えと密教の教えは同等であると考え、円珍は、両者は同じ教えを説いているが密教の方が大事であると考えた。この密教に対する考え方の違いから、円仁と円珍が亡くなった後、天台宗内部で対立が生じる。993年、円仁派と円珍派の対立が続く中、円珍派は比叡山を降りて独立し、園城寺(三井寺)で独自の動きを見せるようになる。比叡山を総本山としていた天台宗が分裂して、比叡山に残った円仁派を山門派、園城寺(三井寺)に移った円珍派を寺門派と呼ぶようになった。両社の対立は、教上の対立を越えて、度重なる武力闘争や政治闘争にまで発展。園城寺は何度寺を焼かれても復活するその様子から「不死の寺」という異名を持つほど激しい争いがあった。
・欠裂……決裂?
・端緒(たんしょ)……始まり。
第153章 皇統第172代[神倭第75代]鳥羽天皇
・・・・・ 269
・安倍泰親……安部泰親(あべのやすちか)。安倍晴明の5代目の子孫で、平安時代末期の高名な陰陽師。
・看破(かんぱ)……隠されていること、背後にあるものを見やぶること。見あらわすこと。
・殺生石(せっしょうせき)…… 殺生石は、那須岳の丘陵が湯本温泉街にせまる斜面の湯川にそったところにある。 平安の昔、帝愛する妃に「玉藻前」という美人がいたが、天竺(インド)、唐(中国)から飛来してきた九尾の狐の化身だった。帝は日に日に衰弱して床に伏せるようになり、やがて、陰陽師の阿倍泰成がこれを見破り、上総介広常と三浦介義純が狐を追いつめ退治したところ、狐は巨大な石に化身し毒気をふりまき、ここを通る人や家畜、鳥や獣に被害を及ぼした。やがて、源翁和尚が一喝すると、石は三つに割れて飛び散り、一つがここに残ったと言われ、その石が「殺生石」と伝えられている。
第154章 皇統第177代[神倭第80代]六条天皇
・・・・・ 270
・専横(せんおう)……わがままで横暴なふるまい・態度。
・承久の乱……承久3年(1221)、後鳥羽上皇が鎌倉幕府の討滅を図って敗れ、かえって公家勢力の衰微、武家勢力の強盛を招いた戦乱。
・武門(ぶもん)……武士の家筋。武家。
・帰(き)する……①最終的にある一つのところにおちつく。…という結果になる。②帰順する。帰依する。
・承久の乱(じょうきゅうのらん)……承久3年(1221)、後鳥羽上皇が鎌倉幕府の討滅を図って敗れ、かえって公家勢力の衰微、武家勢力の強盛を招いた戦乱。
・清和天皇(せいわてんのう)……源頼朝は、第56代清和天皇を起源とする清和源氏の嫡流であると名乗っていた。
・駆(か)る……①追い立てる。追い払う。しいてさせる。 ②走らせる。急がせる。 ③(主として受身の形で)感情・希望などが心を強くとらえる。
・大権(たいけん)……明治憲法下、広義には、天皇が国土・人民を統治する権限(=統治権)。狭義には、憲法上の大権として、帝国議会の参与によらず輔弼ほひつ機関のみの参与によって行使する天皇の権限。
・奪取(だっしゅ)……奪い取ること。
・皮相(ひそう)……①うわべ。表面。②真相をきわめず、表面のみを見て下す浅薄な判断。
・介在(かいざい)……両者の間に他のものがはさまってあること。
・策動(さくどう)……ひそかに策略をめぐらし行動すること。
・真個(しんこ)……まこと。全く。
第155章 皇統第184代[神倭第87代]後堀河天皇
・・・・・ 271
・熱誠(ねっせい)…… 熱情から出るまごころ。きわめて深いまごころ。
・披見(ひけん)……文書などをひらいて見ること。
・参籠(さんろう)……神社・仏寺などに昼夜こもって祈願すること。おこもり。
・扶植(ふしょく)……①うえつけること。②たすけたてること。扶持すること。
・立宗(りっしゅう)……宗教・宗派が打ち立てられ、 生まれること。立教。開宗。
・咤呮尼天(だきにてん)……吒枳尼天の誤りか? 荼枳尼天、荼吉尼天とも。サンスクリット語の音写。
仏教の鬼神で、密教では、胎蔵界曼陀羅外院にあって、大黒天に所属する夜叉神。死者の肉を食う夜叉(鬼神)の類。日本では稲荷神の本地仏とされ、愛知県の豊川稲荷(妙厳寺)に祀られる。
・使嗾(しそう)……指図してそそのかすこと。けしかけること。
・擲(なぐ)る……①(握り拳で)横ざまに力をこめて打つ。強く打つ。なぐる。①なげつける。なげとばす。なげうつ。③なげやりにする。手をぬく。
・宣(せん)する……布告する。
第156章 皇統第194代[神倭第97代]後醍醐天皇
・・・・・ 273
・一班(いっぱん)…… ①組織の一つの区分。 ②班の全体。
・臥薪嘗胆(がしんしょうたん)……仇をはらそうと長い間苦心・苦労を重ねること。転じて、将来の成功を期して長い間辛苦艱難すること。
・撲滅(ぼくめつ)……うちほろぼすこと。ほろぼし絶やすこと。
・令(れい)する……命令する。申しつける。言いつける。
・寄寓(きぐう)……①他人の家に身を寄せること。 ②かりのすまい。寓居ぐうきょ。
・後村上(ごむらかみ)天皇……南北朝時代の南朝の天皇。後醍醐天皇の第7皇子。1339年(延元4)吉野の行宮で即位後、賀名生・男山・河内観心寺などに移り、住吉行宮に没す。(在位1339〜1368)
・光明(こうみょう)天皇…… 南北朝時代の北朝の天皇。後伏見天皇の皇子。後醍醐天皇が吉野に遷った後、足利尊氏が擁立。(在位1336〜1348)
・後光厳(ごこうごん)天皇……北朝第4代の天皇(在位1352~71)。南朝後村上天皇の天下一統が破れ、足利氏がふたたび北朝を樹立することになり、その要請により、親王宣下も、神器もなくして、広義門院の院宣で皇位についた。在位中、南朝軍に攻められ、美濃小島、近江武佐などに難を避けた。その後、南朝に幽居中の兄・崇光上皇が帰還し、後光厳天皇がその皇子に譲位したことから、兄弟の間に深刻な不和が生まれたが、足利氏の支持によって、以後この天皇の子孫が4代を相続した。
・抹殺(まっさつ)……①こすり消してなくしてしまうこと。 ②事実・存在などを否認し、完全に消し去ること。
・消除(しょうじょ)……消えてなくなること。取り消すこと。
・久遠(くおん)…… ①時の無窮なこと。永遠。くおん。 ②広く大いなること。
・局(きょく)……当面の情勢。事態。
・後亀山(ごかめやま)天皇……南朝最後の天皇。後村上天皇の第2皇子。1392年(元中9・明徳3)、南北両朝合一により北朝の後小松天皇に譲位、帰京。(在位1383〜1392)
・後小松(ごこまつ)天皇……南北朝末期・室町初期の天皇。後円融天皇の第1皇子。1392年(明徳3)、南北朝が合一。譲位後、院政。(在位1382〜1412)(1377〜1433)
・喧轟(けんごう)……騒がしく響き渡る。また、騒がしい。
・上御一人(かみごいちにん)……天皇の尊称。
・正閏(せいじゅん)……①平年と閏年。②正統と閏統。正位と閏位。「南北―論」/閏統(じゅんとう)……正統でない系統。傍系であること。
第157章 皇統第201代[神倭第104代]後土御門天皇
・・・・・ 274
・下賜(かし)…‥高貴の人が、身分の低い人に物を与えること。
・紛々(ふんぷん)……入り乱れてまとまりのないさまのこと。
・軫念(しんねん)……天子がきめ細かく心配されること。
・暴威(ぼうい)…‥荒々しい勢い。乱暴な威勢。
・所以(ゆえん)…‥わけ。いわれ。理由。
・囲繞(いじょう)……ぐるりととり巻く。
・慄然(りつぜん)……恐れおののくさま。恐ろしさにぞっとするさま。
第158章 皇統第203代[神倭第106代]御奈良天皇
・・・・・ 277
・後奈良天皇(ごならてんのう)
・家宰(かさい)…… 家の仕事を、その家長にかわって取りしきる人。
・厳存(厳存)……確かに存在。
・際会(さいかい)……事件や機会などにたまたまであうこと。
・暴虐(ぼうぎゃく)……むごいことをして人を苦しめること。また、そのさま。
・際会(さいかい)……重大な事件や時機にたまたま出あうこと。
・相伝(そうでん)……代々受け継いで伝えること。
・土賊(どぞく)……その土地の賊徒。土匪(どひ)。
・全(まった)きを得(え)る……安全である。無事である。
・偏(ひとえ)に……①ただそのことだけをするさま。いちずに。ひたすら。②原因・理由・条件などが、それに尽きるさま。もっぱら。
・勅定(ちょくじょう)……天子がみずから定めたこと。また、天子の命令。勅命。
・陰険(いんけん)……①表面は何気なく装いながら、心の内に悪意を隠しているさま。②意地悪そうに見えるさま。
・奈辺(なへん)……どのあたり。どのへん。どこ
第159章 皇統第204代[神倭第107代]正親町天皇
・・・・・ 278
・幾何(いくばく)も……(あとに係助詞「も」と打消しの語を伴って、数量・程度が多くないことを表す。)あまり。
第160章 皇統第207代[神倭第110代]明正天皇
・・・・・ 279
・下乗(げじょう)……これより先は神域なので乗物からおりて入りなさい。
・毀(こぼ)す……①破壊する。②本来の働きを損なう。故障させる。③つぶす。④くずす。
・令(れい)する……命令する。言いつける。
・依然(いぜん)……もとのままであるさま。前のとおりであるさま。
・罪科(つみとが)……①つみととが。②法律に照らして処罰すること。しおき。
・衰微(すいび)……衰えてかすかになること。盛んでなくなること。
第161章 皇統第212代[神倭第115代]中御門天皇
・・・・・ 279
第162章 皇祖皇大神宮沿革[其の一]
・・・・・ 280
・沿革(えんかく)……物事の移り変わり。今日までの歴史。変遷。
・追懐(ついかい)……昔の事や人などをあとから思い出してしのぶこと。追憶。追想。
・資とする……①たすけとする。役立てる。②費用を給する。もとでを与える。
・文(ぶん)にする……言葉を文書で示す。
・大根(おおね)……①物事の大もと。根本。②太い矢の根。③ダイコンの古名。
・元祖(がんそ)……①家系の最初の人。始祖。②物事を最初に始めた人。鼻祖。創始者。③仏教の一宗の開祖。特に、法然をさす。
・勅定(ちょくじょう)……天子がみずから定めたこと。また、天子の命令。勅命。
・書(か)き誌(しる)す……①文字や文章などを書きつける。書きとめる。記録する。
・乞祈……「乞い祈む」(こいのむ)……神に請い祈る。ねがい祈る。神仏に祈願する。請願する。
・無極(むきょく)……①果てがないこと。限りのないこと。また、そのさま。無窮。②人知を越えた果てしないところ。転じて、宇宙の根源のこと。
・奉安(ほうあん)……尊いものをつつしんで安置すること。
・御船代(みふなしろ)……「船代」は、伊勢の皇大神宮の樋代(神社で神体を納める器)を奉安(=尊いものをつつしんで安置する)する箱。石船の形に作られる。
・中真(なかみ)
・登(のぼ)す……参上させる。召し寄せる。
・目(もく)する?……①目をつける。みなす。②認める。評価する。③注目する。「自する」か?
・爾今(じこん)…… 今からのち。今後。以後。
・屋根を鵜草にて葺き合せ……鵜の羽を葺草にして葺いた屋根
・奉捧(ほうほうorほうぼう?)……「奉」「捧」とも、両手で捧げ持つようすを表す。
・纂(つむ)らせ……書物を編纂する、まとめたり、集めたりする、編集する
・合祀(ごうし)……二柱以上の神を一つの神社にまつること。また、ある神社にまつってあった神を、他の神社に移して一緒にまつること。合祭。
・祀祭(しさい)……「神や祖先を祀る、祭る」という意味で、ほぼ同義です。しかし、「祀る」は主に神仏を祀る場合に用いられ、「祭る」はより広く、神や祖先、さらには一般的に「祭り」と呼ぶイベント全般を指す際に使われます。(AI回答)
・差遣(さけん)……公の使者として派遣すること。
・敵仇(?)……「敵」 (かたき) は、競争相手や、戦や争いの相手、恨みを持つ相手を指します。また、結婚の相手や、親しい関係を築いている相手を指す場合もあります。
「仇」 (あだ) は、主に恨みを持つ相手を指します。親の仇を討つ、恩を仇で返すなどのように、恨みや復讐の対象として使われることが多いです。(AI回答)
・害禍(さまたぎ)……妨害する。邪魔する。
第163章 別祖神宮沿革
・・・・・ 302
・懸族(けんぞく)……天孫降臨に際して、天から降臨した神々の一族を指す場合や、神社の祭祀を奉仕する一族を指す場合もあります。(AI回答)
第164章 皇祖大神宮沿革[其の二]
・・・・・ 303
・日神(にちじん)……日の神。日輪。「ひのかみ」と読む場合は、太陽神。また特に、天照大神。
・亊(じ)う……仕える。「亊」/出来事、事柄。成り行き。人の努め。仕事。
・明応(めいおう)……1482~1501年
・長享(ちょうきょう)……1487~1489年
・享禄(きょうろく)……1528~1532年
・宝暦(ほうれき)……1751~1764年
・慶安(けいあん)……1648~1652年
・明暦(めいれき)……1655~1658年
・大得(?)
・丸形真(?)……「真丸・真円」は、全くまるいこと。正しくまるいことだから、「丸形真」は、その意味か?
・御国(おくに)…… ①江戸時代、大名の領地の尊敬語。 ②地方。田舎いなか。③他人の出身地の尊敬語。
・天覧(てんらん)……天皇が御覧になること。叡覧。
・不孝(ふこう)……孝行でないこと。親につかえる道を守らないこと。(※ ただ、「不孝にも大没落に及」では、意味がつながらない。「不幸」の書き間違いかも?)
・往古(おうこ)……遠い過去。おおむかし。
・乗打(のりうち)…… 馬や駕籠かごに乗ったままで(貴人の前を)通り過ぎること。
・幷(へい)……主に「あわせる」、「並ぶ」といった意味で使われます。また、接続詞として「さらに、その上、なお」という意味で使われることもあります。(AI回答)
・坊都(ぼうと?)……古代日本において都城を構成する都市区画を表す言葉です。具体的には、条坊制と呼ばれる都市計画において、東西に走る道路(坊)に囲まれた街区を指します。(AI回答)*ここでは(坊主ーぼうず)という意か?
第165章 神政復古準備
・・・・・ 312
・裡(り)……物の内側。ある状態のうち。(「裏」の俗字だが、「うち」の意だけに用いる。)
第166章 皇統第217代[神倭第120代]光格天皇
・・・・・ 313
・澎湃(ほうはい)……水のみなぎりさかまくさま。転じて、物事が盛んな勢いで起こるさま。
・揺曳(ようえい)……ゆらゆらとなびくこと。また、あとあとまで長く、その気分や痕跡などが残ること。
・乃(すなわ)ち……①その時。②むかし。あのころ。当時。(即ち/則ち)
・一の(いちの)……第一の
・勅授(ちょくじゅ)……太政官の奏聞を待たず、勅旨によって位勲を授けること。律令制では、五位以上の叙位、六等以上の叙勲をいう。明治憲法下では、従四位以上の叙位。
・澆世(ぎょうせい)……「澆=軽薄」から、道徳の薄れた人情軽薄な世の意味か。
・輔弼(ほひつ)……①天子の政治をたすけること。また、その役。 ②明治憲法の観念で、天皇の行為や決定に関し進言し、その結果について全責任を負うこと。
・真人(しんじん)……まことの道を体得した人。
・陽(よう)に……表から見えるところでは。うわべでは。
・陰(いん)に……かげで。内々。
・咫尺(しせき)……①近い距離。②接近すること。貴人にお目にかかること。
・維新(いしん)……①物事が改まって新しくなること。政治の体制が一新され改まること。 ②明治維新のこと。
・布衣……「ふい」/官位のない人。庶人。「ホイ、ホウイ」/ ①庶民が着用する麻布製の衣服。
・徴(しる)して……①めじるしとする。心覚えとする。あとかたをつける。②前兆を示す。
・統理(とうり)……統べおさめること。
・委細(いさい)……こまかくくわしいこと。また、くわしい事情。
・宣示(せんし)……人に明らかにしめすこと。広く天下に告げしめすこと。公示。明示。
・天明(てんめい)……明けがた。夜明け。
・非(ひ)なり……不利だ。うまくいかない。
・抗(こう)する……抵抗する。さからう。あらがう。
・末法万年……仏滅後、その教えの効力が消滅する長い年月。(「末法」は、仏の滅後、その教えの功力が消滅する時期。「万年」は、①一万年。長い年月)
・陽(よう)に陰(いん)に……あるときはこっそりと,あるときは表立って。常に。/「陽に陰に」と同じ?
・彼岸(ひがん)……①春分の日・秋分の日を中日とする各7日間。また,この時期に営む仏事。②迷いを脱し、生死を超越した理想の境地。悟りの境地。涅槃。③目標に至った理想的状態。凡人を超えた,高度な境地。
・暴挙(ぼうきょ)……乱暴でむぼうなふるまい。
・隠忍自重(いんにんじちょう)……ひたすら我慢して軽々しい振る舞いを慎むこと。
・更(あらた)めて…… 今までのものを新しくかえる。とりかえる。
・尊崇(そんすう)……尊びあがめること。
・英明(えいめい)……優れて賢いこと。
・厄(やく)……①災難。わざわい。②厄年」に同じ。
第167章 皇統第220代[神倭第123代]明治天皇
・・・・・ 319
・宝算(ほうさん)……天皇の年齢。聖寿。
・偉(い)に……大きくりっぱなこと。すぐれていること。また、そのさま。
・内侍所(ないしどころ)……① 平安時代、三種の神器の一つである八咫鏡を安置した所。温明殿にあり、内侍が奉仕した。賢所。
・登極令(とうきょくれい)……天皇の践祚および即位礼と大嘗祭・元号などに関して規定した旧皇室令。1909年(明治42)公布。
・体(たい)する……心にとめて守る。目上の人の教えや意向に沿って行動する。のっとる。
・詔勅(しょうちょく)……天皇が意思を表示する文書。詔書と勅書と勅語。
・上諭(じょうゆ)……①君主のおさとし。 ②明治憲法下で、法律・勅令・条約・予算などを公布する時、その冒頭に付して天皇の裁可を表示した語。
・泰西(たいせい)……西洋諸国の称。西洋。
・頓挫(とんざ)……中途で行きづまって、くじけること。計画や事業などが中途で進展しなくなること。
・措(お)きて……~を除いて。~以外に。
・逐次(ちくじ)…‥順次
・慮(おもんばか)る……周囲の状況などをよくよく考える。思いめぐらす。
・嘉納(かのう)……①献上品などを目上の者が快く受け入れること。②進言などを高位の者が喜んで聞き入れること。
・須(もち)い……もちいる
・隠忍(いんにん)……苦しみを心中に隠して堪え忍ぶこと。
・輔佐(ほさ)=補佐
・形勢(けいせい)……①様子。ありさま。②変化していく物事のなりゆき。対立する物事の勢力関係。情勢。
・一斑(いっぱん)……①一つのまだら。特に、豹の毛皮などのまだらをいう。 ②一部分。
・拝誦(はいしょう)……読むことの謙譲語。つつしんで読むこと。拝読。
・汲(く)む……①器物や手のひらなどを使って、水などをすくい取る。②酒・茶などを器につぐ。③人の心の内を推し量る。立場・事情などを察してよく理解する。思いやる。酌量する。④物事の趣を味わう。⑤精神・立場などを受け継ぐ。
・巷間(こうかん)……まちの中。また世間。ちまた。
・忖度(そんたく)…‥おしはかる。
・真個(しんこ、しんか)……まこと。全く。
・布(し)く……①一面に平らに広げる。②設置する。敷設する。③配置をする。④隅々まで行き渡らせる。⑤広く行き渡る。一面に広がる。⑥力を広く及ぼす。治める。
・蓋(けだ)し……①まさしく。ほんとうに。たしかに。②ひょっとしたら。もしや。
・半(なか)ば過(す)ぎ……· 全体のだいたい半分を過ぎたあたり、を指す表現。
・一見(いっけん)……①一とおり見ること。ちらっと見ること。 ②一度あうこと。③(副詞的に)ちょっと見たところ。
第168章 皇統第221代[神倭第124代]大正天皇
・・・・・ 327
・麾下(きか)…… ①将軍直属の家来。旗下。 ②ある人の指揮の下にあること。また、そのもの。部下。幕下。
第169章 登極令の変遷
・・・・・ 325
・統管(とうかん)……統合管理すること。ばらばらの物を一つにまとめ管理すること。
・爾今(じこん)……今からのち。今後。以後。
・思惟(しい)……①考えること。思考。②哲学で、感覚・知覚と異なる知的精神作用。
第170章 『大正の代はあぢさゐの花盛り』
・・・・・ 336
・神慮(しんりょ)……神のみこころ。
・使嗾(しそう)……指図してそそのかすこと。けしかけること。
・不例(ふれい)……貴人の病むこと。
・蟠踞(ばんきょ)……①わだかまりうずくまること。 ②広大な土地を領し勢力を振るうこと。
・撹乱(かくらん)…… かきみだす、混乱させること。
・画餅(がべい)に帰(き)す……計画などが失敗し、むだ骨折りに終わる。
・策謀(さくぼう)……はかりごと。
・脚下(きゃっか)……足の下。あしもと。
・延(ひ)いて……それからひきつづいて。それが原因になって。それをおしすすめて。
・麾下(きか)…… ①将軍直属の家来。旗下。 ②ある人の指揮の下にあること。また、そのもの。部下。幕下。
・参(さん)ずる…… ①参上する。まいる。 ②参禅する。
・差(さ)し遣(つか)わす……さしむけてつかわす。派遣する。
・号(ごう)する……①言いふらす。自分で言う。名乗る。 ②名づける。称する。号をつける。 ③実際以上に大きく言う。
・華府(かふ)……華盛頓(ワシントン)の略称。
・斧鉞(ふえつ)を加(くわ)える……弱者が自分の力をわきまえずに、強敵に抵抗することのたとえ。「蟷螂」はかまきり、「斧」は前足の意。かまきりが前足を上げて、大きな車に立ち向かうという意か。
・まします(在す・坐す)……おわします。いらっしゃる。「在ます」の尊敬語。
・探査(たんさ)……さぐり調べること。
第171章 皇統第222代[神倭第125代]裕仁天皇 良子皇后宮
・・・・・ 341
・漂(ただよ)う……①・水に浮かんでゆらゆらする。ゆらいで一つ所に定まらない。②迷いあるく。さまよう。③安定していない。ふわふわしている。しっかりしていない。④ひるむ。たじたじする。⑤ある雰囲気や匂いなどがあたりに流れる。
・還元(かんげん)……①根源に復帰させること。もとに戻すこと。②〔化〕(reduction)酸化された物質を元へ戻すこと(すなわち酸素を奪うこと)。
・腐心(ふしん)……(ある事を実現しようとして)心をいため悩ますこと。苦心。
・機運(きうん)……時のまわりあわせ。おり。時機。
・還元(かんげん)……①根源に復帰させること。もとに戻すこと。 ②〔化〕(reduction)酸化された物質を元へ戻すこと(すなわち酸素を奪うこと)。広い意味では、物質に電子が与えられる変化を総称する。↔酸化。
・全(まっと)うする……完全にはたす。なしとげる。また、完全に保つ。
・帰還(きかん)…… ①もどること。特に、戦地・軍隊などから故郷へ帰ってくること。
・宣(のたま)う……①(尊者が下位の者に)言ってきかせる。 ②「言う」の尊敬語。おっしゃる。
・目睫(もくしょう)…… ①目と睫まつげ。 ②転じて、極めて接近している所。目前。
・体(たい)する…… 心にとめて守る。目上の人の教えや意向に沿って行動する。のっとる。
・効(こう)を奏(そう)する……効果をあらわす。効き目が現れる。
・順次(じゅんじ)…‥①次々に順序どおりにすること。順ぐり。順々。
・訓諭(くんゆ)……教えさとすこと。
・叩頭(こうとう)……頭を地につけて拝礼すること。叩首。
・帰順(きじゅん)……反逆の心を改めて、服従すること。
・股肱(ここう)……ももとひじ。転じて、手足となって働く、君主が最もたよりとする家臣。
・邪心(じゃしん)……よこしまなこころ。不正な心。
・翻(ひるがえ)す……①さっと裏返しにする。②態度などを急に変える。
第172章 天地御和合[天の岩戸開き]
・・・・・ 343
・黙過(もっか)……知っていながら黙って見すごすこと。
・嘉納(かのう)……他人の進言・献上物などをよろこんでうけ入れること。
・再三再四(さいさんさいし)……「再三」は、二度も三度も、たびたび、しばしばの意。「再四」は「再三」を強めた言葉。
・速(すみやか)に……間を置かずに。「可能な限りはやく」との意味合いで用いられる。
・本分(ほんぶん)を全(まっと)うする……自分のすべきことをしっかりやる
・諄々乎(じゅんじゅんこ)……丁寧に繰り返し教え戒める/「諄諄」は、「①ていねいに繰り返し教えいましめるさま。 ②まめやかにいそしむさま。」。「乎」は、 状態を表す語に付けて語調を強める語。「洋々―」
・神集(かみつどい)……①神々が集まる。②神々を集める。
・専断(せんだん)……自分だけの意見で勝手に物事をとりはからうこと。
・妄動(もうどう)…… 理非の分別もなく行動すること。ぼうどう
・相携(あいたずさ)える……互いに手をつなぐこと。
・帰還(きかん)……戻ること。
・相共(あいとも)に……共に、一緒に、共々に。
・退散(たいさん)…… ①あつまっている人々が退き散ること。 ②逃げ散ること。のがれ去ること。
・波瀾(はらん)……①大小の波。波濤(はとう)。②激しい変化や曲折のあること。また、そうした事態。騒ぎ・もめごとなど。
・曲折(きょくせつ)……①曲がりくねること。折れ曲がること。②物事がさまざまに入り組んで変化をすること。また、込み入った事情。
・特命(とくめい)……特別の命令・任命。
・誓約(せいやく)……固く誓うこと。また、その誓い。
・奉(たてまつ)る……①上位の人に差し上げる。献上する。②その動作を受ける人を主として、尊敬語として用いる。㋐「飲む」「食う」の尊敬語。召し上がる。㋑「着る」の尊敬語。お召しになる。㋒「乗る」の尊敬語。お乗りになる。③(補助動詞)動詞の連用形に付いて謙譲の意を添え、その動作の及ぶ相手を敬う。…申し上げる。…さしあげる。
・嘉納(かのう)……①献上品などを目上の者が快く受け入れること。②進言などを高位の者が喜んで聞き入れること。
・潔(いさぎよ)しとしない……自分が関わる事柄について、みずからの信念に照らして許すことができない。
・斧鉞(ふえつ)を加(くわ)える……弱者が自分の力をわきまえずに、強敵に抵抗することのたとえ。「蟷螂」はかまきり、「斧」は前足の意。かまきりが前足を上げて、大きな車に立ち向かうという意から。
・跼蹐(きょくせき)……跼天蹐地(きょくてんせきち)の略。身の置き所もない思いをすること。肩身が狭くて世を恐れはばかって暮らすこと。跼蹐。/「跼」は背をかがめる、「蹐」は抜き足で歩く意)頭が天に触れるのを恐れて背をかがめて歩き、地が落ちくぼむのを恐れて抜き足で歩く意。
・鬱憤(うっぷん)……心に積もる怒り。抑えに抑えたうらみ。
・把持(はじ)……①手にしっかり持つこと。手に握ること。 ②〔心〕(→)保持に同じ。
・急進主義(きゅうしんしゅぎ)……現状を中途半端にではなく急速かつ根本的に変革しようとする立場。
・慮(おもんばか)る……よくよく考える。考えはかる。思いめぐらす。
・捧呈(ほうてい)……手で捧げて差し上げる。
・諌言(かんげん)……① 目上の人の欠点や過失を指摘して忠告すること。また、その言葉。② いましめること。きびしく注意すること。
・互譲(ごじょう)……互いに譲りあうこと。
・俟(ま)つ……頼りとする。期待する。よる。
・隠然(いんぜん)……表面にはっきり現れないが、勢いや重みのあるさま。
・斡旋(あっせん)……①事が進展するよう、人と人の間をとりもつこと。世話。周旋。 ②〔法〕労働法上、労働争議調整の一方法。
・定(さだ)まる……①確定する。規定される。きまる。②一定のしきたりとなる。慣例として定着する。③配偶者などとして正式にきまる。④平定・安定する。おちつく。おさまる。しずまる。
・反逆(はんぎゃく)……権威・権力などにさからうこと。
・兼(か)ねて…… 以前から。前から。前もって。かねがね。
・先般(せんぱん)……さきごろ。せんだって。
・誓約(せいやく)…… 誓って約束すること。また、その約束。
・使神(ししん)……誓約使神は、日本神話において、天照大御神(アマテラス)と素戔嗚尊(スサノオ)が誓いを交わす際に現れた三柱の女神、宗像三女神のことです。(AI回答)
・答礼使(とうれいし)……相手からの使節(大使)の来訪に対して、返礼として派遣される使節のことです。
・渡欧(とおう)……欧州へ渡航すること
・答礼(とうれい)……相手の礼に答えて礼をすること。また、その礼。返礼。
・漸進(ぜんしん)……段階を追って次第に進むこと。
・微恙(びよう)……気分が少しすぐれないこと。軽い病気。
・国魂神(くにたまのかみ)……国土を経営する神。大国主神など。くにみたま。
・正使(しし)……主たる使者。主任の使者。↔副使
・途次(とじ)……みちすがら。みちみち。途中。
・隈(くま)…… ①道や川などの湾曲して入り込んだ所。 ②奥まって隠れた所。すみ。 ③色と色とが相接する所。光と陰との接する所。ぼかし。陰翳いんえい。 ④秘めているところ。隠していること。 ⑤かたすみ。へんぴなところ。 ⑥欠点。
・宝座(ほうざ)……〔仏〕蓮華れんげの座。蓮座。仏座。
・玲瓏(れいろう)玉(たま)の如(ごと)き……①宝石や金属が触れ合ったときのように、澄みきった美しい音や声を立てるさま。 ②宝石のように、美しく澄みきっているさま。
第173章 人類界建替建直し準備
・・・・・ 348
・根拠(こんきょ)…… ①ある言動のよりどころ。もと。また、議論などのよりどころ。②本拠。ねじろ。
・神庭(かむにわ)……神を祭る場所。祭場。祭壇。神域。
・掉尾(ちょうび/慣用読:とうび)……①尾をふるうこと。 ②物事や文章の終りに至って勢いのふるい立つこと。転じて、最後。
・無二無三(むにむさん)……①〔仏〕法華経に説く、成仏の道はただ一乗であって、二乗も三乗もないこと。 ②ただ一つだけで他に類のないこと。唯一無二。 ③脇目もふらず、ひたすらなさま。しゃにむに。
・遭難(そうなん)……わざわいにあうこと。災難にであうこと。
・傀儡(かいらい)…… ①あやつり人形。くぐつ。でく。 ②転じて、人の手先になってその意のままに動く者。
・放埓(ほうらつ)……勝手気ままにふるまうこと。
・贖罪(しょくざい)…… ①体刑に服する代りに、財物を差し出して罪過を許されること。 ②犠牲や代償を捧げることによって罪過をあがなうこと。
・中道(なかみち)……①道のなかほど。途中。②まんなかの道。 ③登山者が山の中腹を横にめぐること。
・策(さく)する……はかりごとを立てる。画策する。
・国威(こくい)……国の威光。
・発揚(はつよう)……さかんにあらわすこと。ふるいおこすこと。精神や気分を高めること。
・進発(しんぱつ)……戦場などに向かって出発すること。
・則(のっと)る……則としてしたがう。模範としてならう。
・正(しょう)……ちょうどぴったり。まさしく。まさに。/「同日正」は、「同日ぴったり」の意味か。
・惹起(じゃっき)……事件・問題などをひきおこすこと。
・呼応(こおう)…… ①一方のものが呼べば相手が応答すること。 ②互いに気脈を通ずること。
・掉尾(ちょうび)……①尾をふるうこと。 ②物事や文章の終りに至って勢いのふるい立つこと。転じて、最後。「―の勇を奮う」
第174章 駛身界及限身界の将来
・・・・・ 355
・垂示(すいじ)……①教えを説くこと。
・推知(すいち)……ある事からおしはかって知ること。
・課(か)す……割り当てる
・偏狭(へんきょう)……①せまいこと。狭小。 ②度量のせまいこと。
・盲目(もうもく)……①目が見えないこと。 ②物事の弁別(見分け)のつかないこと。
・亡(なく)す…… ① ない状態にする。不要な物などをないようにする。また、置き忘れたり見失ったりして必要な物を失う。 .
・罪過(ざいか)……罪や過失。
・消散(しょうさん)……消え散ること。消えてなくなること。また、消し散らすこと。
・幕下(ばっか)……①張った幕の下。陣営。 ②大将の唐名。 ③将軍・大将軍の敬称。 ④将軍の配下に属するもの。また、将軍のひざもと。 ⑤家臣。家来。配下。
・極限(きょくげん)…… ①行きついたぎりぎりのところ。それ以上はないところ。はて。極度。
・峻厳(しゅんげん)……極めてきびしいこと。
・吾人(ごじん)……①われ。わたくし。 ②われわれ。われら。
・鎬(しのぎ)を削(けず)る……はげしく切り合う。また、はげしく争う。
・趨勢(すうせい)……物事の進み向かう様子。動向。なりゆき。
・錯(あやま)る……①いりまじる。入り組んでまじわる。 ②あやまる。まちがえる。
・勃興(ぼっこう)……急に勢いが強くなること。勃然としておこること。
・霄壌(しょうじょう)……天と地。(「霄壌の差」/天と地ほどの大きなへだたり。雲泥うんでいの差。)
・将(はた)また……「将」は、①ひょっとすると。もしや、②上の意をうけて、これをひるがえす意を表す。 ㋐しかしながら。そうはいうものの。㋑それとも。あるいは。 ③上をうけて、それと同様であることを表す。やはり。
・議(ぎ)……相談すること。
・喧(やかま)しい……①騒がしい。静かでない。そうぞうしい。 ②煩わしい。めんどうである。
・足らざる……足りない、十分ではない、充足していない、
・善処(ぜんしょ)……物事をうまく処置すること。
・招(まね)く……①手で合図して人を呼ぶ。さしまねく。②人を誘ってよびよせる。礼をつくして呼ぶ。招待する。③ひきおこす。こうむる。うける。
・不可避(ふかひ)……さけることができないこと。
・弥縫(びほう)……①おぎない合わせること。 ②失敗・欠点などを一時的にとりつくろうこと。
・善導(ぜんどう)……教えて、よい方にみちびくこと。
・推知(すいち)……ある事からおしはかって知ること。
第175章 日の本将来の概況
・・・・・ 360
・久古(?)
・隠匿(いんとく)……①包み隠すこと。秘密にすること。かくまうこと。②隠れた悪事。心中に蔵する罪悪。隠悪。
・無恙(むよう、ぶやう)……つつがないこと。異状ないこと。また、そのさま。無事。
・落伍(らくご)……①隊伍からおくれ脱落すること。 ②力量が足りなくて仲間や競争相手からおくれ、ついてゆけなくなること。人後におちること。
・蠢動(しゅんどう)…… ①虫などのうごめくこと。 ②転じて、取るに足りないものが策動すること。
・撹乱(かくらん)……かきみだす。混乱させること。
・弥(いや)が上(うえ)にも……なおその上に。さらに。いっそう・ますます。
・異彩(いさい)……異なった色どり。転じて、他とひどく異なった趣。きわだってすぐれた様子。
・天変(てんぺん)……天空に起こる異変。暴風や雷・日食・月食の類。
・地妖(ちよう)……地上の怪しい変異。
第176章 海外諸国将来の概況
・・・・・ 362
・緩急(かんきゅう)……ゆるやかなことときびしいこと。遅いことと速いこと。 ②急なこと。危急の場合。まさかの場合。
・宜(よろ)しき……適当なこと。適切なこと。
・先後(せんご)……さきとあと。また、事の順序。前後。
・短時日(たんじじつ)……みじかい日かず。少しの日数。
第177章 現界の建直し
・・・・・ 363
・令(れい)する……命令する。申しつける。言いつける。
・大詔(たいしょう)渙発(かんぱつ)……「大詔」は、 詔の尊敬語。「渙発」は、詔勅を広く天下に発布すること。「大詔―」
・万般(ばんぱん)……すべての物事。百般。万端。
・輔佐(ほさ)…… 人に付いてその仕事をたすけること。また、その役の人。
・総社(そうじゃ)……参拝の便宜のため、数社の祭神を1カ所に総合して勧請神社。一国の総社のほか、寺院・荘園の総社などがある。また、鎮守または一の宮が総社を兼ねたこともある。
・骨子(こっし)…… ①ほね。 ②中心。要点。眼目。
・編出する(編み出す)…… ①新しい物事を考え出す。また、作り出す。 ②編み始める。
・鑑(かんが)みる……先例に照らして考える。他とくらべあわせて考える。
・治下(ちか)……ある政権の支配下にあること。統治下。
第178章 駛身神霊界の建直し
・・・・・ 365
・功(こう)…… ①なしとげたしごと。その結果。てがら。いさお。 ②経験・仕事などの蓄積。年功。
・名(な)を遂(と)とげる…… 名声を十分にあげる。
・真解(しんかい)し……「真実に解き明かす」「深く理解する」という意味で使われます。具体的には、物事の真実や本質を理解する、納得する、などを指します。(AI回答)
第179章 みろくの世の出現
・・・・・ 366
・年所(ねんしょ)……年数。年月。歳月。
・三十二相八十種好(さんじゅうにそうはちじっしゅごう)……仏の姿の 32の特徴を数え上げた語。釈迦像がインドで制作されはじめてまもなく起った考え方で,『大智度論』などの経典に述べられている。三十二相をさらに詳説したのが八十種好相で,『大般若経』などに述べられている。仏の外形的な特徴とともに宗教的な理想を示している。経典により多少の相違がある。
・天皇の大御代(おおみよ)を厳御代(いかしみよ)の足御代(たらしみよ)に……?.
・轗軻(かんか)……好機にめぐまれず志を得ないこと。世にいれられないこと。困窮すること。不遇。不運。
・則(のっと)る……のりとしてしたがう。模範としてならう。
・魂魄(こんぱく)……(死者の)たましい。精霊。霊魂。
・まにまに……そのままに任せるさま。物事の成行きに任せるさま。まにま。ままに。
・順(まつろ)いて……①服従する。従いつく。②服従させる。従える。
・薫陶(くんとう……徳を以て人を感化し、すぐれた人間をつくること。
・埒(らち・らつ)…… 馬場のかこいの低い垣かき。転じて、物事のくぎり。限界。
・寸毫(すんごう)……きわめてわずかなこと
・紊(みだ)る…… ①秩序を失わせる。入りまじらせる。②ばらばらにする。散乱させる。③平静さを失わせる。混乱させる。④騒動を起こす。兵を起こす。⑤(自動詞として古くミダレルと同じに使われた)保たるべき秩序が失われる。収拾がつかなくなる。平静でなくなる。
・延(ひ)いては……それからひきつづいて。それが原因になって。それをおしすすめて。
・仲秋(ちゅうしゅう)…… (秋の3カ月の真ん中の意。)陰暦8月の異称。
Copyright © 2020 solaract.jp. All Rights Reserved.

-1-scaled-2.jpg)